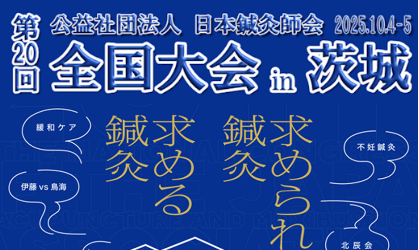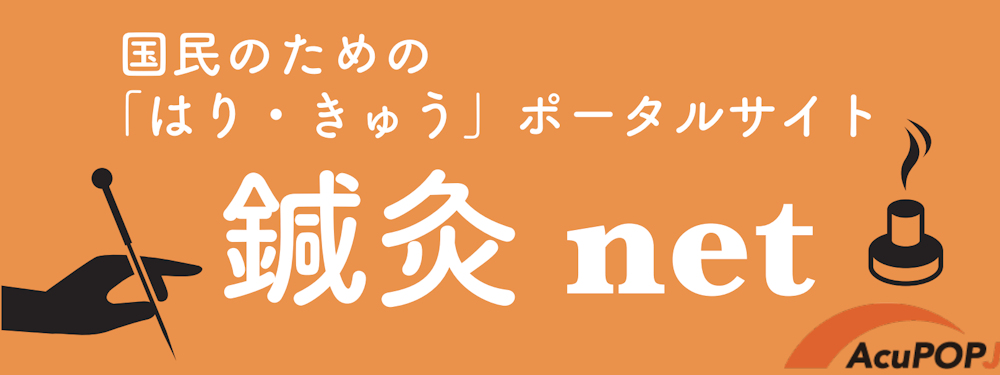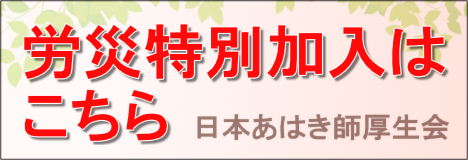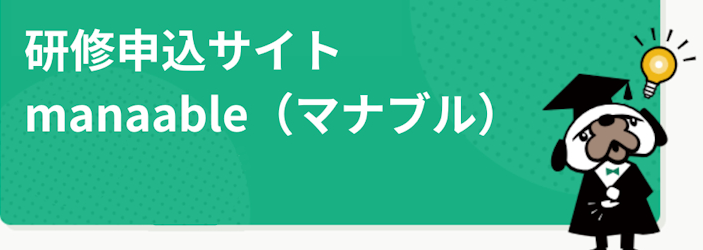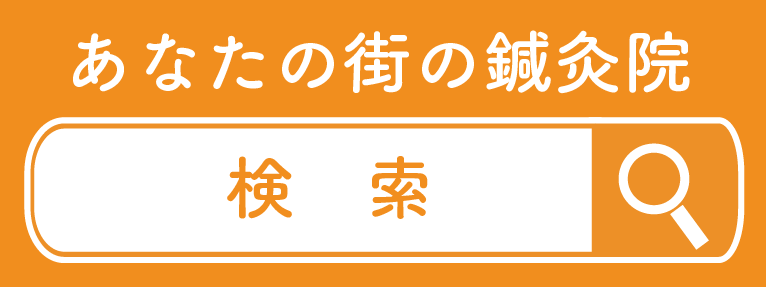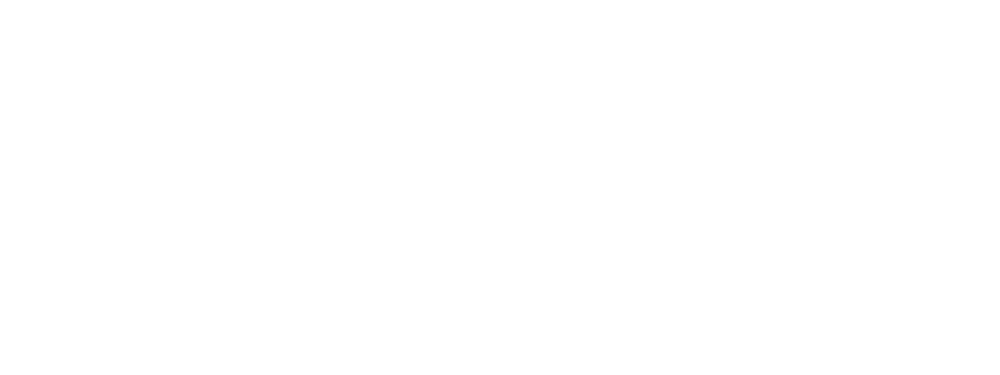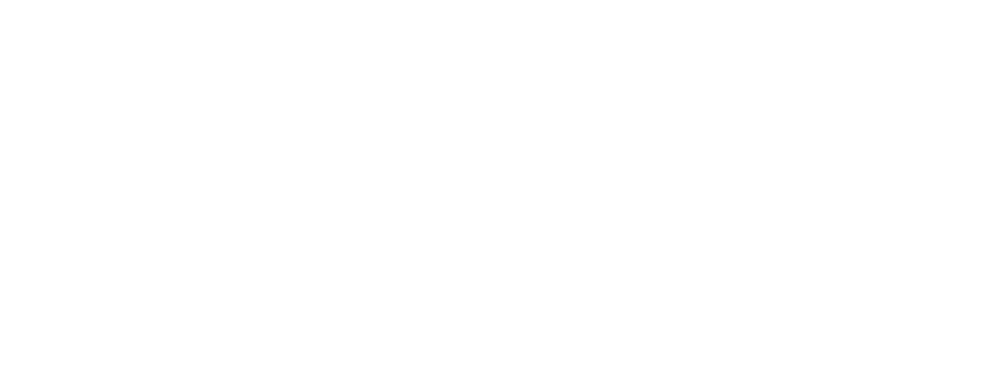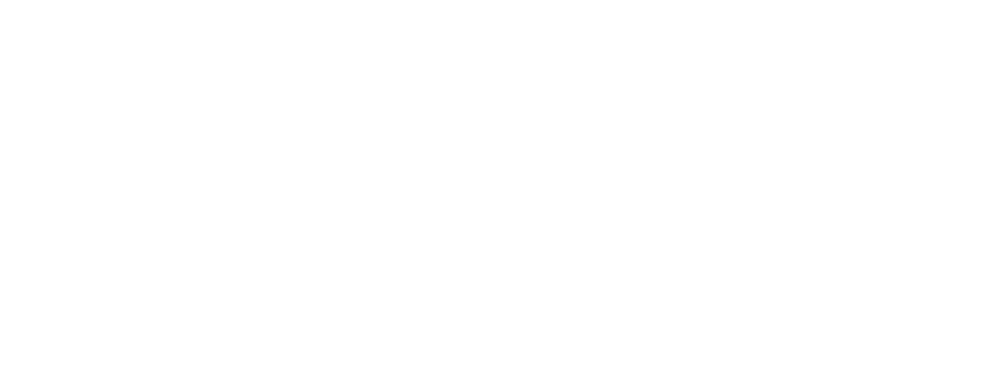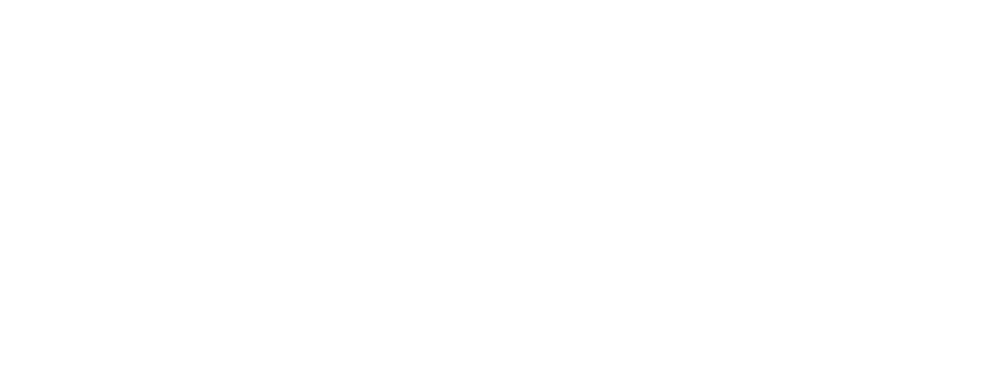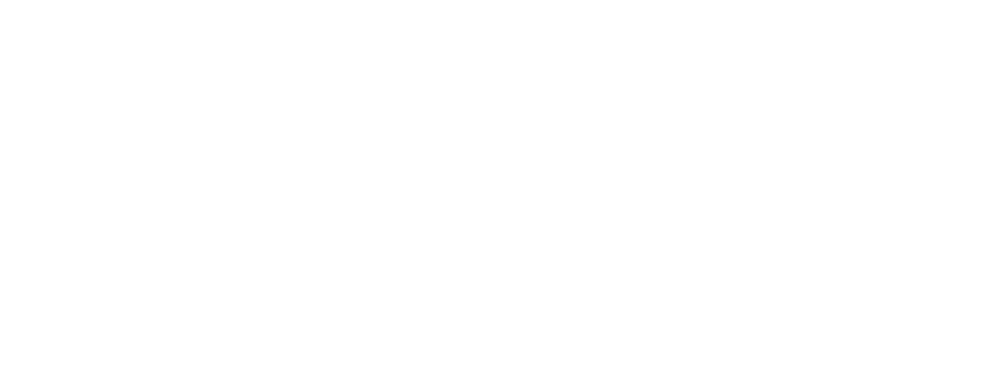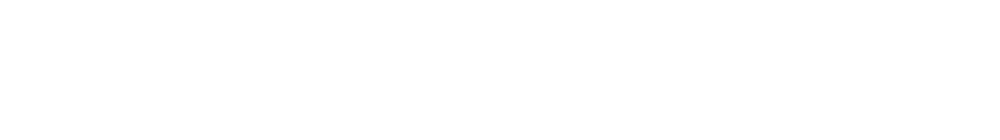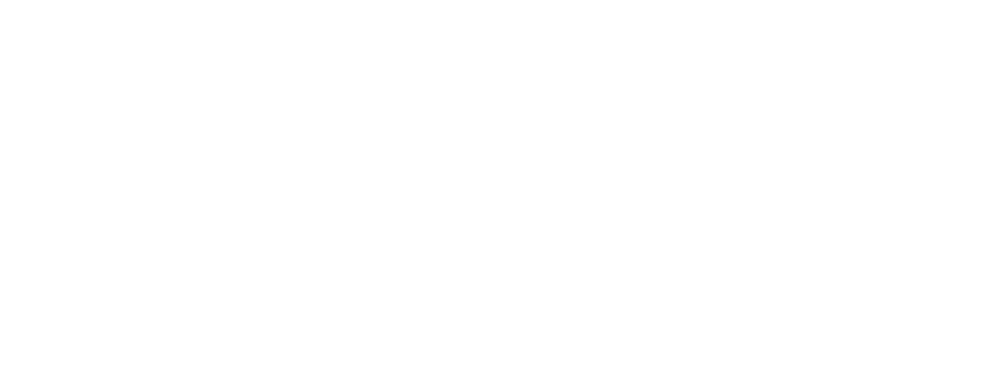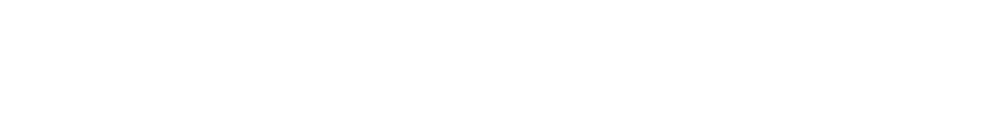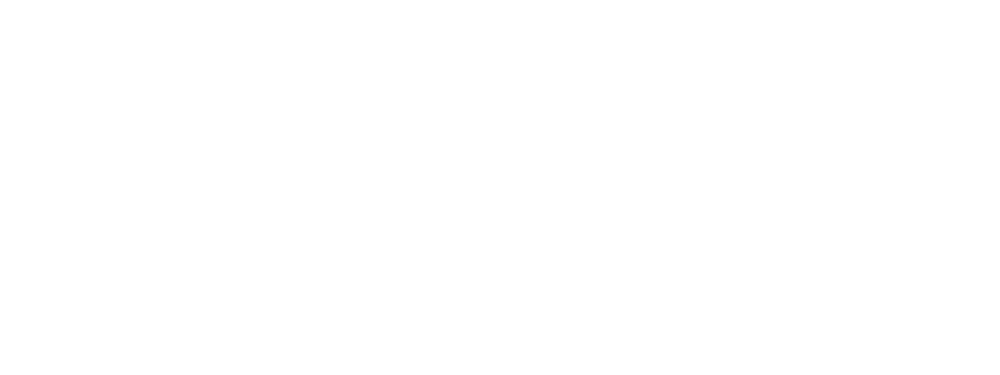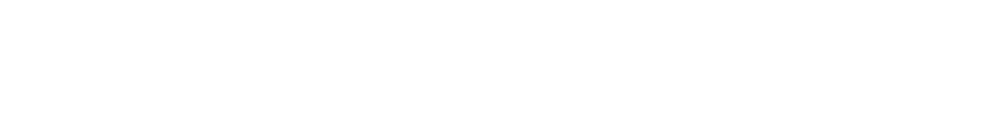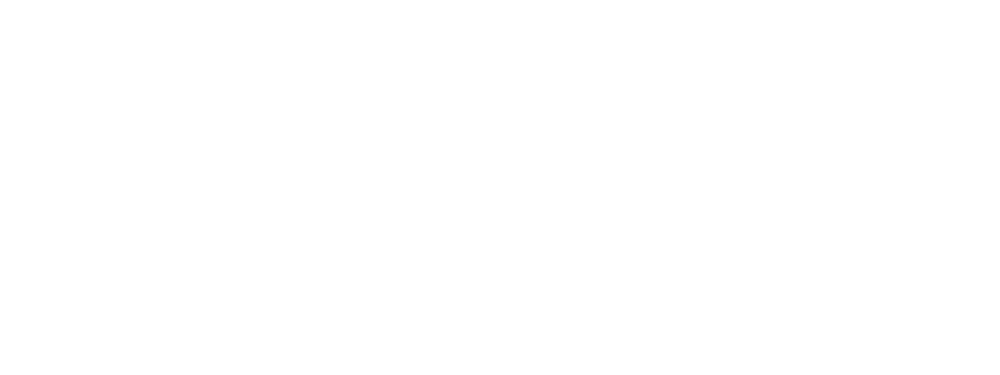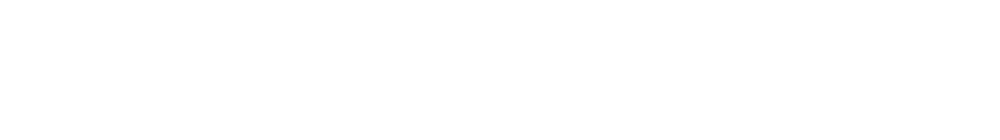霊枢勉強会報告
報告『黄帝内經靈樞』 決氣(けっき)第三十
講師 :日本鍼灸研究会代表 篠原 孝市 先生日時 :令和六年(2024年)12月 08日(日) 第45回
会場 :大阪府鍼灸師会館 3階
出席者: 会場参加者 14名 WEB参加者 24名
○『黄帝内經靈樞』 決氣(けっき)第三十
**澀江抽齋(しぶえ ちゅうさい)の『靈樞講義(れいすうこうぎ)』をテキストとしている。 それによると、丙午(ひのえうま)九月初六 (弘化三年〈1846年〉九月六日) にこの篇の講義を行ったと記されている。 180年ほど前のことである。
余談ではあるが、この講義が行われた1846年の前後は、1837年 大塩平八郎の乱、1853年 アメリカ使節ペリーが浦賀に来航、 そしてこの講義の歳から22年後の1868年には明治時代がはじまる。
*馬玄臺( ばげんだい・馬蒔【ばじ】も同一人物 )はこの篇について、こんなふうに言う。
「決論 一氣六名之義、 故名萹。」
( *ひとつの氣は六つの名前を持っている、それを論究したものである。 )
*張志聰(ちょうしそう)という人は、このように言っている。
「決、分也。 決而和、 故萹名 「決氣」、 謂氣之分判爲六、 而和合爲一也。 」
( *ひとのからだを氣として把握する。 氣というものはひとつなのだが、その様々なはたらきにより六つの名前に分けている。 しかしこの六つの名前のものは、もともとは別々のものではなく同じ氣である。 )
○『黄帝内經靈樞』 決氣(けっき)第三十・ 第二章
○01 歧伯曰。 02 兩神相搏。
01 歧伯(きはく)曰(いわ)く、 02 兩神(りょうしん)相搏(あいまじ)わりて、
(解説)
*02節の「兩神(りょうしん)相まじわりて」とは、男女の房事のことである。 もっと抽象的に言うと陰の気と陽の気が交差しあうことによって、というふうなことであろう。
*明刊無名氏本(みんかんむめいしぼん)『新刊黄帝内經靈樞』によると「 02 兩神相摶 」となっているが「 02 兩神相搏 」が正しい。
*郭靄春(かくあいしゅん)氏は「相搏(あいう)つ」というのは、近づくという意味だと言う。 兩神というのは陰と陽のふたつの気を表す。 つまり男女の気のことである。 それが互いに相近づいてというふうになる。
*仁和寺本『太素(たいそ)』では、「 02 兩神相薄 」になっている。
*楊上善(ようじょうぜん)という人は、“ 雌雄二靈之別, 故曰兩神(りょうしん), 陰陽二神相得, 故謂之薄。 」
【**雌雄(しゆう)の二靈(にれい)之(こ)れを別(わか)ちて、 ゆえに兩神(りょうしん)と曰(い)う。 陰陽二つの神(しん)が相得て、 ゆえにこれを薄( はく・ぴったりとくっつく )と謂(い)う。 】
○03 合而成形。 04 常先身生。 05 是謂精。
03 合せて形(けい)を成(な)す。 04 常(つね)に身(み)に先(さき)立ちて生ずる、 05 是(これ)を精(せい)と謂(い)う、 と。
(解説)
*03節の「形(けい)」と言うのは外形のことである。 目で見ることができ、触ってわかる、そういうものを「形(けい)」と呼ぶ。
*04節の「常に身に先立ちて生ずる」とは五藏(ごぞう)などが出来る前の形(けい)、両神が相まじわりて出来た「形(けい)」の中に根源的な気が出来るのだと言う。 これを「精(せい)」と呼ぶのだと05節で言っている。
*考えてみればひとが生まれてくるというのは、「兩神(りょうしん)相搏(あいう)つ」、男女というものがないと、ひとは存在することが出来ないと気づく。 それは、考えかたによっては、とてもおもしろい。 ひとは自らの意志で生きているように思うのだが、実はその存在そのものが、前の世代に依拠(いきょ)していて、そこからは逃れられない。 親も子もなくひとりで生きてきたと言う人もあるが、本当はそういうことを人は出来ない。 常に先行するものがあり、それらが「合(あわ)せて形(けい)を成す」肉体を形成するのである。
*04節の「身(み)」は、「形(けい)」と同じ。
*04~05節は、乳児として産まれて来た時に、はじめにあるのが「精(せい)」だと言っている。 「精(せい)」というものは混じり気のない、とても純粋なもので男女の気(き)というものを受け継いでいる。 しかし乳児は「精(せい)」だけでは生きてはいけない。 この後、ものを食べたり、考えたりすることで「精(せい)」を支えるものが生ずる。
*張介賓の注を読んでおく。
「 兩神(りょうしん)とは陰陽(いんよう)なり。 搏(はく)とは交わるなり。 精(せい)とは天一(てんいつ)の水(みず)なり。 凡(およ)そ陰陽(いんよう)合わせて萬物(ばんぶつ)と成る。 先(ま)ず精(せい)從(よ)り始まらざる無し。
故(ゆえ)に曰(い)う。 “常に身に先立ちて生ずる。 是(これ)を精(せい)と謂(い)う” と。
按(あん)ずるに本神篇(ほんじんへん)に曰(いわ)く、 “ 兩精(りょうせい)相搏(あいう)つ。 之(こ)れを神(しん)と謂う。 ”と。
而(しか)して此(こ)れに曰(いわ)く (*これとは本篇のこと)
“ 兩神(りょうしん)相搏(あいう)つ。 合わせて形(けい)を成す。 常に身に先だちて生ずる。 是(これ)を精(せい)と謂(い)う ” と。
蓋(けだ)し彼(かれ・ここでは本神篇を言う)は、
精(せい)に由(よ)って以(もっ)て神(しん)を化(か)す、を言い、
此(こ)れ(*この篇を言う)は、
神(しん)由(よ)り以(もっ)て精(せい)に化(か)すを言う。 ”
二者(にしゃ)同じからざるが若(ごと)し。 正(まさ)に以(もっ)て陰陽(いんよう)の互用(ごよう)を明らかにするものなり。 即(すなわ)ち其(そ)の合一(ごういつ)の道(みち)なり。 」
*(張介賓の注の解説)
*もともと、ひとの始まりは「精(せい)」からはじまって、「精(せい)」から「精(せい)」と「神(しん)」が出来る。 精(せい)は腎(じん)の藏(ぞう)を、神(しん)は心(しん)の藏(ぞう)を、次いで肝(かん)と肺(はい)が出来る。 最後に脾(ひ)が形成されるというのが、『靈樞(れいすう)』などに書かれている五藏(ごぞう)の形成状態ということになろう。 なぜ、精(せい)や神(しん)という言葉を使っているのだろうか。 五藏(ごぞう)の名前でたとえば心(しん)の気(き)や肝(かん)の気(き)と言っても構わないのだが、根源的なひとのありかたを説明する時に、このような説明のしかたが良かったのだろう、そんなふうに思う。
*『靈樞(れいすう)』を勉強するのに携えておくとよい三冊
① 劉衡如(りゅうこうじょ)著『靈樞經(校勘本)』
② 『靈樞經校釋(れいすうきょう・こうしゃく)』
③ 郭靄春(かくあいしゅん)氏の『靈樞校注語訳(れいすう・こうちゅう・ごやく)』
*『霊枢』の森を歩いてみませんか。毎月休まず第二日曜午前10時から12時まで、大阪府鍼灸師会館3階です。勉強会の案内につきましては本会ホームページをご確認下さい。
次回は新しい歳、2025年 2月9日(日)、『霊枢』「海論(かいろん) 第三十三」 です。 どの篇でも、気になるところの受講、大歓迎です。 会場はライブ感がありますし、web受講は自宅でも出来ますので、どうぞ。
(霊枢のテキスト〈日本内経医学会 発行,明刊無名氏本〉 は現在1冊の在庫があります。1冊1,600円です。受講申し込み時、または当日、受講受付けにてお問い合わせください)
(霊枢勉強会世話人 東大阪地域 松本政己)