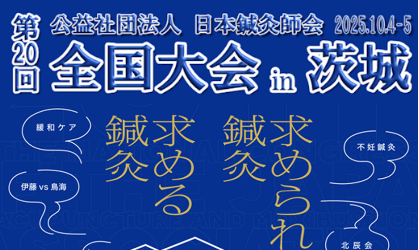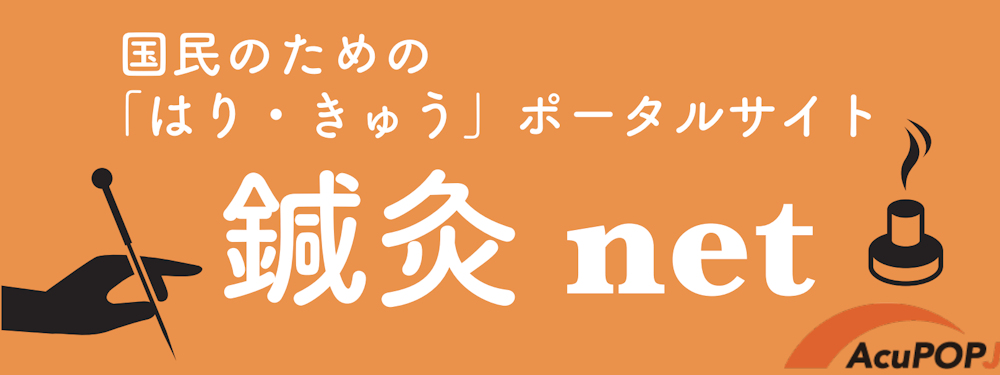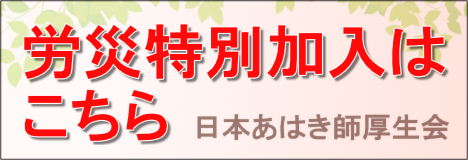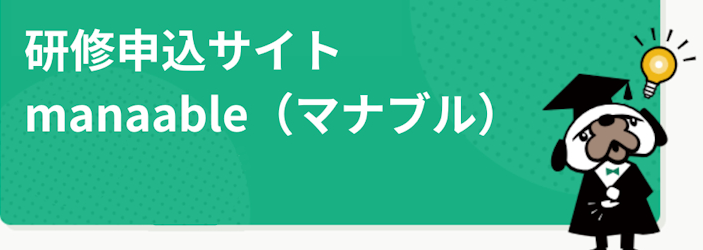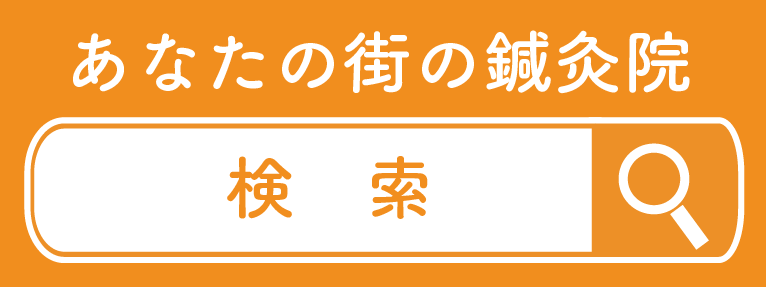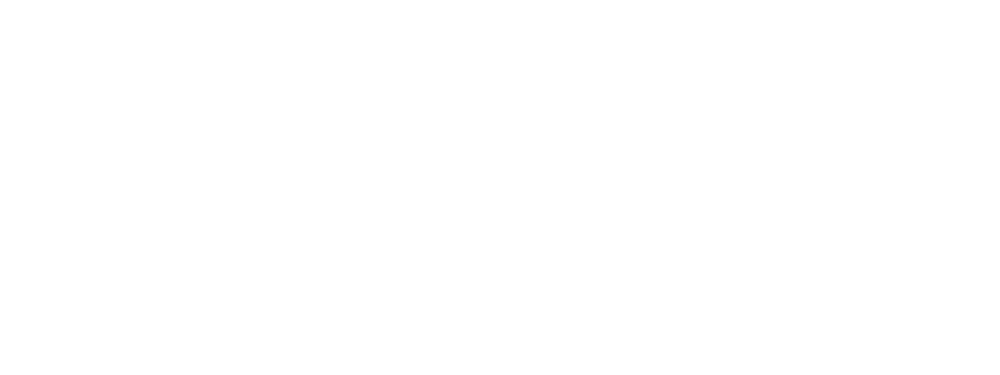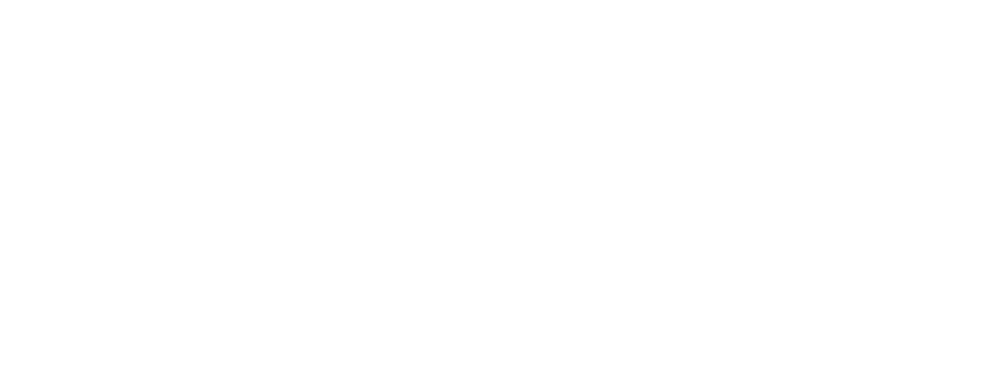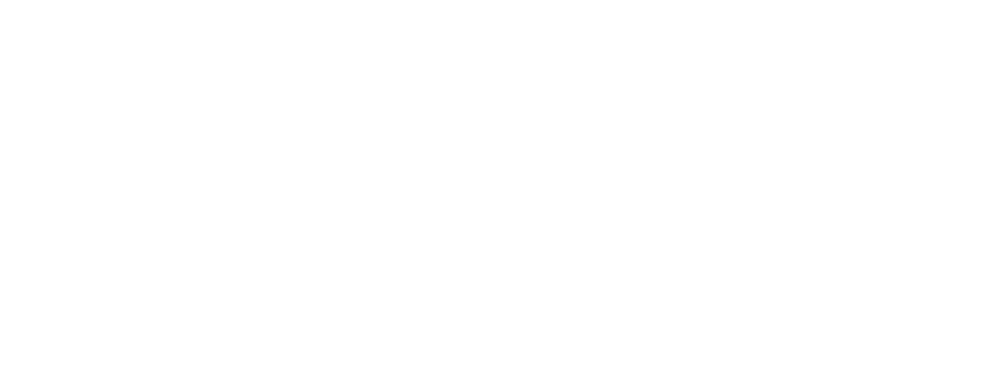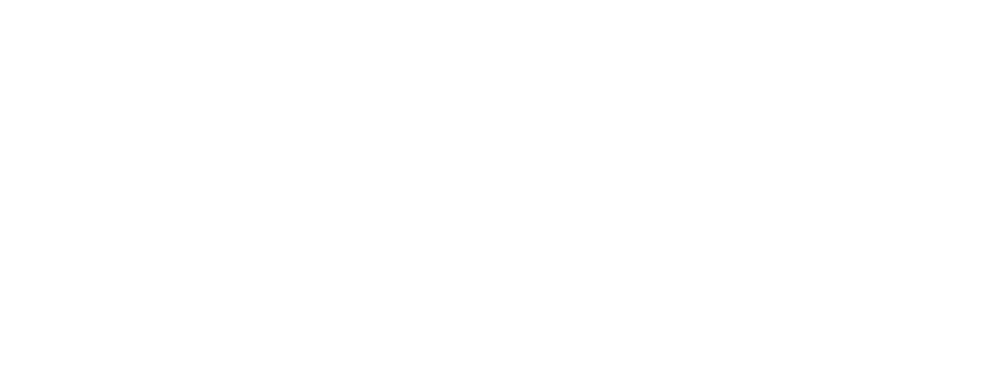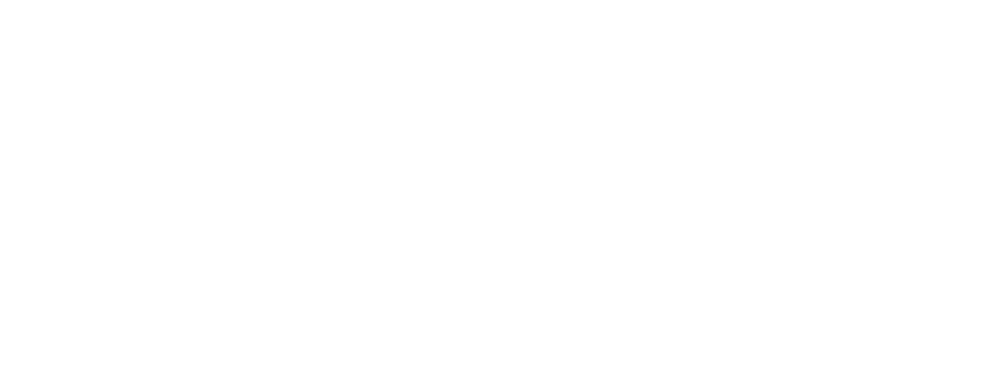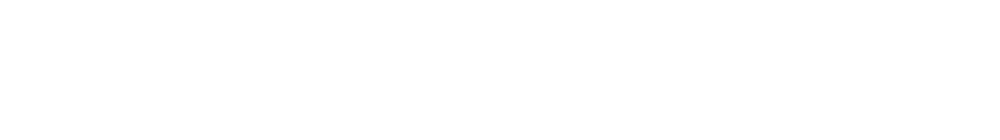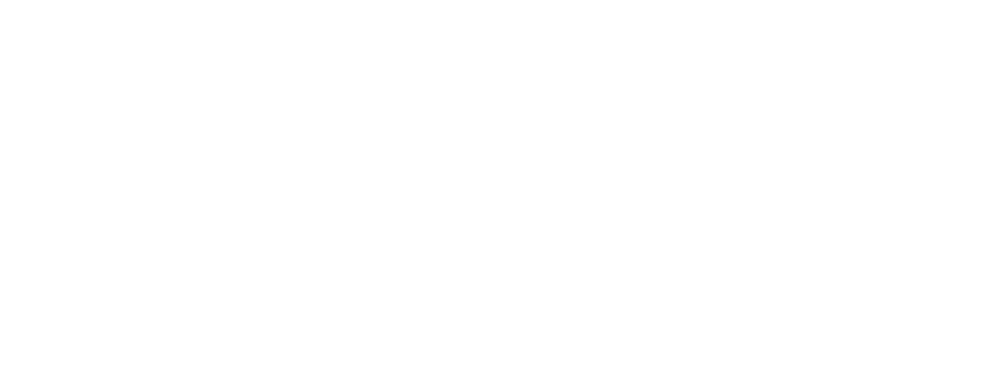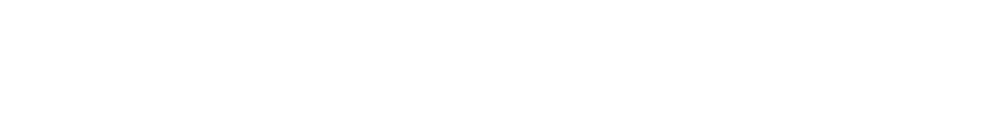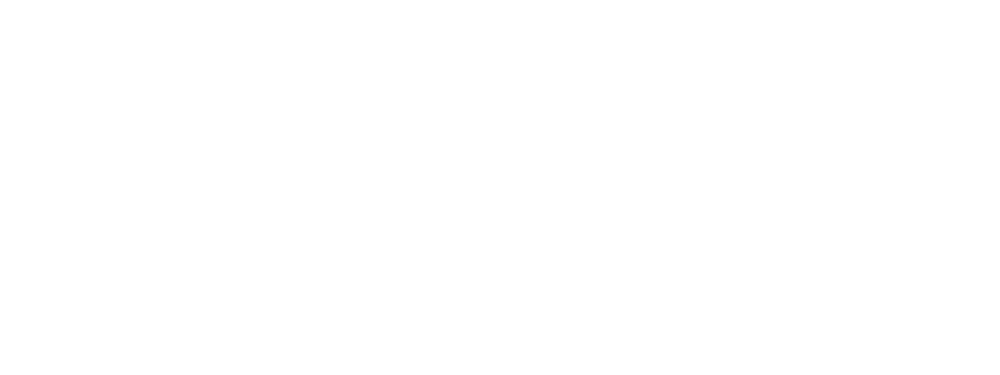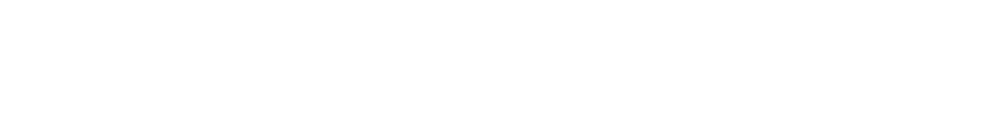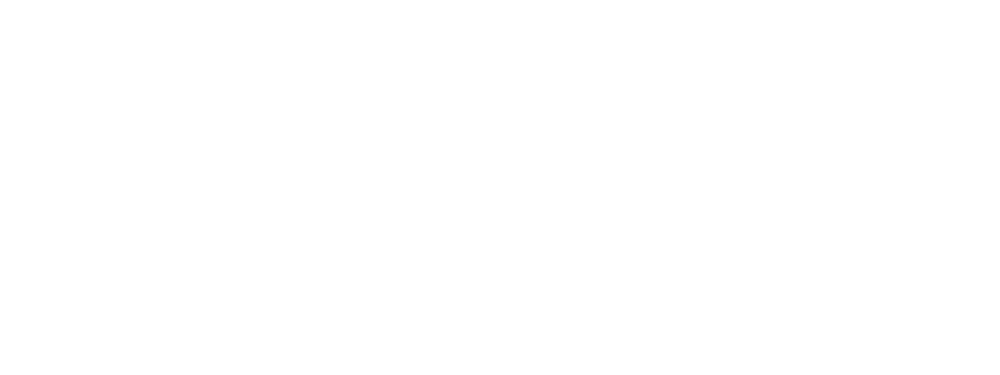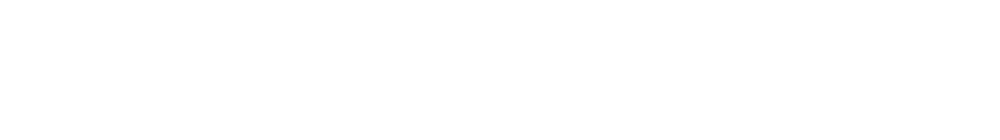霊枢勉強会報告
報告『黄帝内經靈樞』 師傳(しでん)第二十九・ 第一章
講師 :日本鍼灸研究会代表 篠原 孝市 先生日時 :令和六年(2024年)11月 10日(日) 第44回
会場 :大阪府鍼灸師会館 3階
出席者: 会場参加者 15名
○その3
○34 黄帝曰。 35 便病人柰何。
34 黄帝(こうてい)曰(いわ)く、 35 病人に便(べん)なること柰何(いかん)、 と。
(解説)
*35節の「病人に便(べん)なること」とは、患者にとって、もっとも望ましいことということである。 それは具体的に何であるか、それを問うている。
○36 歧伯曰。 37 夫中熱消癉則便寒 38 寒中之屬則便熱。
36 歧伯(きはく)曰(いわ)く、 37 夫(そ)れ中熱(ちゅうねつ)消癉(しょうたん)は則(すなわ)ち寒(かん)に便(べん)なり。 38 寒中の屬(ぞく)は則(すなわ)ち熱(ねつ)に便(べん)なり。
(解説)
*ここでは「寒(かん)」と「熱」が問題となる。 「中熱(ちゅうねつ)」と「寒中(かんちゅう)」という言葉が出てくる。 からだの中に、これはおなかに、と言い変えても良いと思うが、そこに中熱(ちゅうねつ)消癉(しょうたん)という状態がある。 もう一つはそれと対になる寒中(かんちゅう)という状態がある。 これについて張介賓(ちょうかいひん)という人はこのような注を入れている。(*文末のカッコ内に訳文)
「此(こ)の下に皆(み)な治病(ちびょう)の便(べん)なる所を言う。 【 *治療にとって便なること(よろしきこと)をここで述べる 】
中熱(ちゅうねつ)とは、 中(なか)に熱(ねつ)有るなり。 消癉(しょうたん)とは、 内熱(ないねつ)して癉(たん)を爲(な)す。
善(よ)く飢渇(きかつ)して、 日(ひ)に消痩(しょうそう)するなり。 ( *おなかがすいて食物を食べるのだが、だんだんと痩せていく )
凡(およ)そ熱(ねつ)、中(なか)に在(あ)らば、 則(すなわ)ち治(ち)するに寒(かん)をよろしきとする。 寒(かん)中(なか)に在(あ)れば、 則(すなわ)ち治(ち)、熱(ねつ)をよろしきとする。 是(こ)れ皆(み)な病情(びょうじょう)に順(したが)う所以(ゆえん)なり。 」
○39 胃中熱則消穀。 40 令人懸心善飢。
39 胃中(いちゅう)熱すれば則(すなわ)ち穀(こく)を消(しょう)し、 40 人(ひと)をして懸心(けんしん)して善(よ)く飢(う)えしむ。
(解説)
*ここで「中熱(ちゅうねつ)」について述べている。 中熱(ちゅうねつ)には、胃中(いちゅう)を熱するものと、腸中(ちょうちゅう)を熱するものがある。
*ここで胃中(いちゅう)を熱す、ということがどうしてわかるのかを述べている。 穀(こく)を消(しょう)す、ということが、そのあらわれだと言う。 食べても食べてもおなかがすく状態である。
*40節の 「懸心(けんしん)」 について説明する。 からだの中で 「心(しん)」 というものが、あたかも糸で吊り下げられた状態でぶら下がっている。 ゆらゆらと不安定な状態になっている。 このような状態の時、胸が落ち着かない。 このような状態のことを 「懸心(けんしん)」 と言っている。
*張介賓(ちょうかいひん)は39~40節においてこのように言っている。
「消穀(しょうこく)とは、 穀食(こくしょく)消(しょう)し易(やす)し。 ( *食べても食べてもおなかがすく )
懸心(けんしん)とは、胃火上炎(いかじょうえん)し、 心血(しんけつ)やかれしめ ( *原文は、「心血被爍」 )、
而(しか)して懸懸(けんけん)として寧(やす)からず。(*心持が安定しない)
胃熱(いねつ)消穀(しょうこく)す。 故に人をして善(よ)く飢える。 」
○41 臍以上皮熱。
41 臍(へそ)より以上、 皮熱(ひねつ)し、
(解説)
*臍(へそ)より上の皮膚が熱い状態を言う。
*楊上善(ようじょうぜん)という人は、このように言う。 「 此(こ)れより以下、 廣(ひろ)く熱中(ねっちゅう)寒中(かんちゅう)の状(かたち)を言う。 胃中(いちゅう)熱して以(もっ)て消穀(しょうこく)し、 虚(きょ)して以(もっ)て飢えることおおし。 胃(い)は齊(へそ)の上に在(あ)り。 胃中(いちゅう)の食氣(しょっき)、上薫(じょうくん)するが、故(ゆえ)に皮(ひ)熱(ねっ)す。 」
*なにしろおなかに熱がある場合、酒を飲んだ時や食べ物を食べたあとに、おなかをさすったりすることがある。 このような状態が「臍(へそ)より上に皮(ひ)、熱する」という状態である。
○42 腸中熱。 43 則出黄如糜。
42 腸中(ちょうちゅう)熱(ねっ)すれば、 43 則(すなわ)ち黄(こう)を出(いだ)すこと糜(び)の如(ごと)し。
(解説)
*張介賓(ちょうかいひん)はこのように言っている。
「 臍(せい)以上とは、 胃(い)と小腸の分(ぶん)なり。 故(ゆえ)に臍(せい)以上、皮(ひ)熱するものは、 腸中(ちょうちゅう)亦(ま)た熱(ねっ)す。 黄(こう)を出(いだ)すこと糜(び)の如(ごと)しとは、 胃中(いちゅう)濕熱(しつねつ)の氣(き)を以(もっ)て、 小腸(しょうちょう)致(いた)す所に傳(つた)う。 糜(び)は、腐燗(ふらん)なり。 (云々) 」
*「臍(せい)」はへそのこと。
*「黄(こう)」は便(べん)のこと。 「糜(び)」というのは、おかゆのような状態、「黄(こう)出(いだ)すこと糜(び)の如(ごと)し」とはおかゆのような軟便を指す。
○44 臍以下皮寒。
44 臍(へそ)より以下、 皮寒(ひかん)し、
(解説)
*腸中(ちょうちゅう)が熱した場合には、臍(へそ)以下の部分が寒(かん)する。 しかし、ここで44節の「皮寒(ひかん)」は疑義がある。 これは「皮熱(ひねつ)」に変えたほうが良いのではないかという注解者の意見がある。 腸中(ちょうちゅう)が熱しているのだから、皮(ひ)が寒(かん)する、ではなくて皮(ひ)が熱(ねっ)するを採るのが妥当だと考えている人がいる。 渋江抽斎(しぶえ ちゅうさい)も郭靄春(かくあいしゅん)氏も、そちらを採っている。 わたしも、ここは「皮(ひ)熱(ねっ)し」を採りたい。
○45 胃中寒。 46 則腹脹。 47 腸中寒。 48 則腸鳴飧泄。
45 胃中(いちゅう)寒(かん)すれば、 46 則(すなわ)ち腹脹(ふくちょう)す。 47 腸中(ちょうちゅう)寒(かん)すれば、 48 則(すなわ)ち腸鳴(ちょうめい)飧泄(そんせつ)す。
(解説)
*胃中(いちゅう)が寒(かん)という状態がなぜわかるのか、 それはおなかが脹るのを見ればわかる。 そして、腸中(ちょうちゅう)が寒(かん)した場合には、おなかが鳴って、不消化便が出ると、ここでは、そんなことを言っている。
*『霊枢』の森を歩いてみませんか。毎月休まず第二日曜午前10時から12時まで、大阪府鍼灸師会館3階です。勉強会の案内につきましては本会ホームページをご確認下さい。
次回は新しい歳、2025年 1月12日(日)、『霊枢』「腸胃(ちょうい) 第三十一」 から始まります。 どの篇からでも受講して頂きたいです。 会場はライブ感がありますし、web受講は自宅でも出来ますので、どうぞ。
(霊枢のテキスト〈日本内経医学会 発行,明刊無名氏本〉は現在1冊の在庫があります。1冊1,600円です。受講申し込み時、または当日、受講受付けにてお問い合わせください)
(霊枢勉強会世話人 東大阪地域 松本政己)