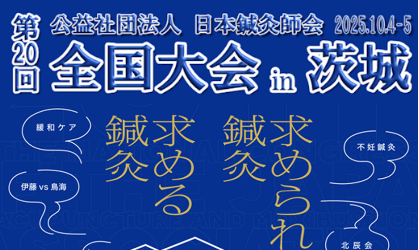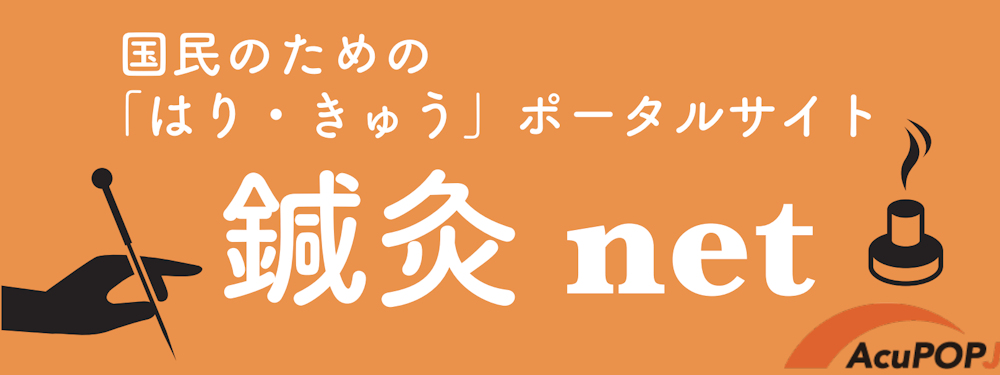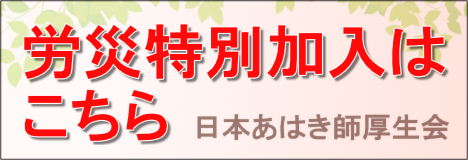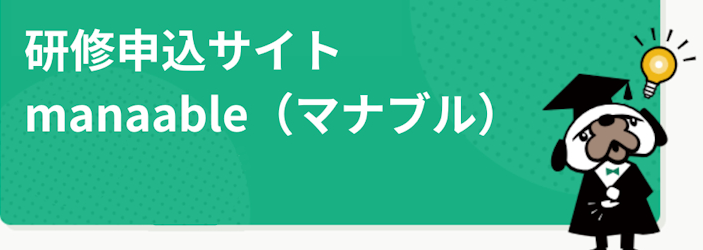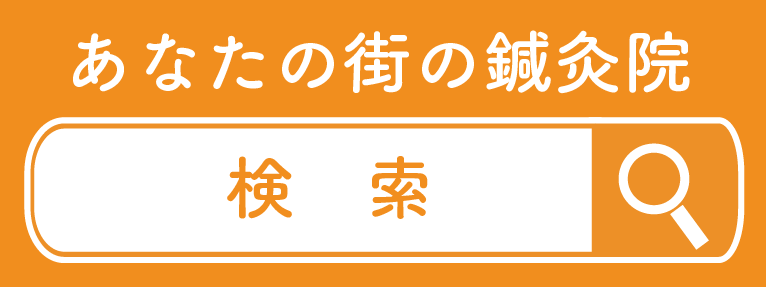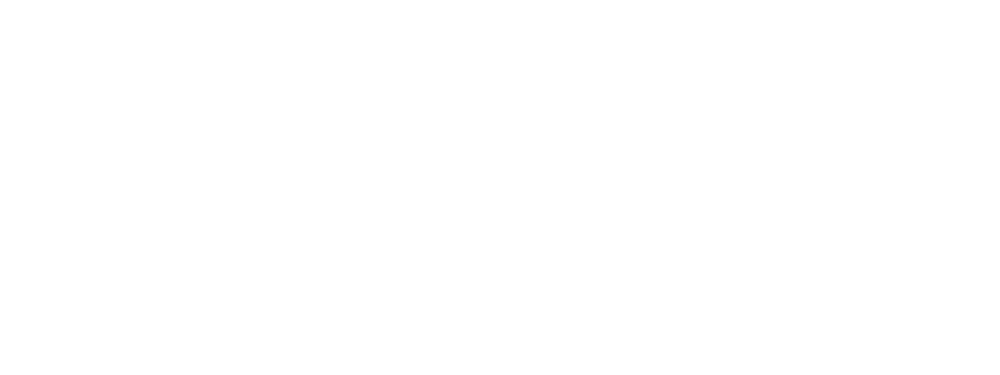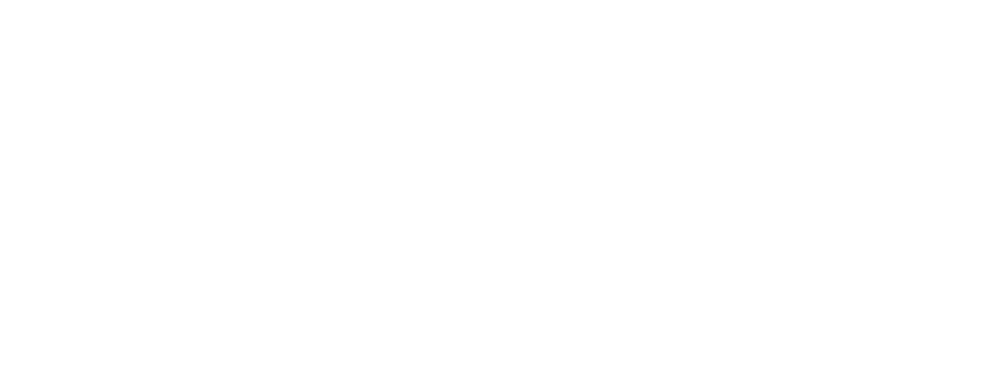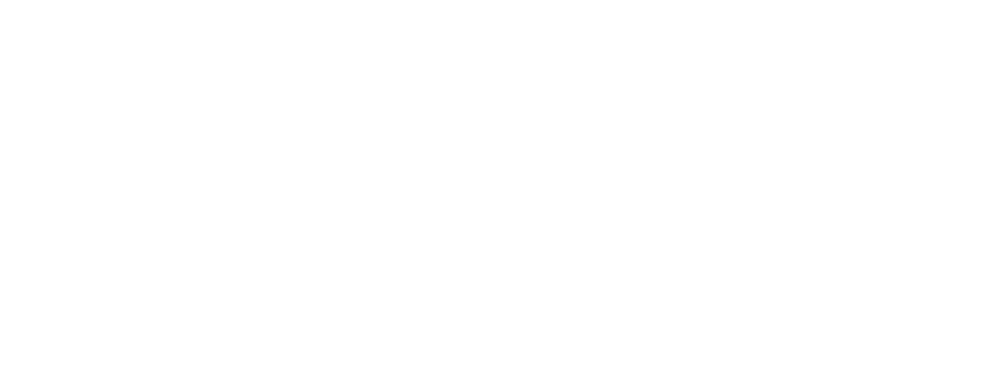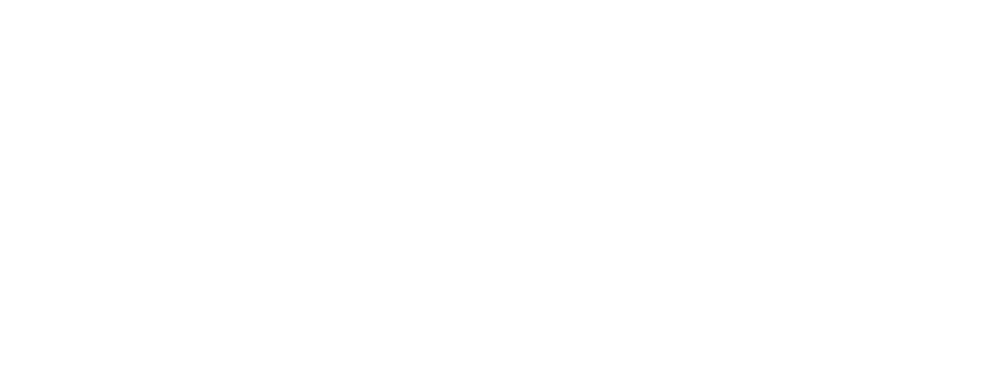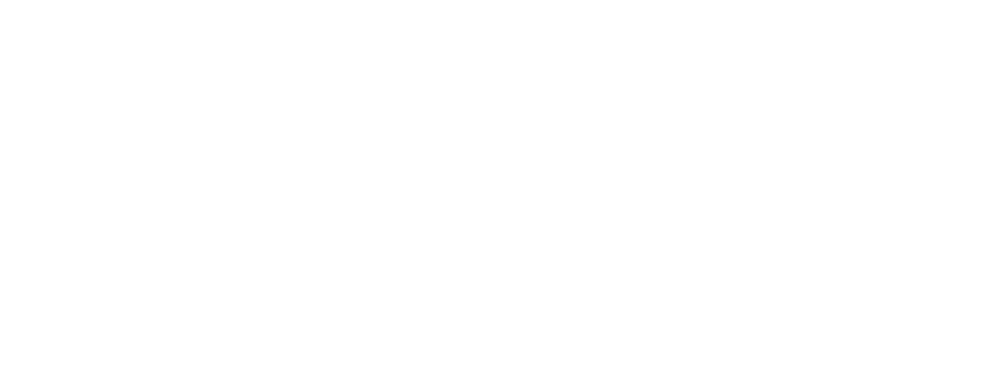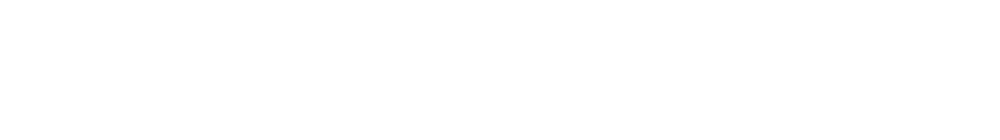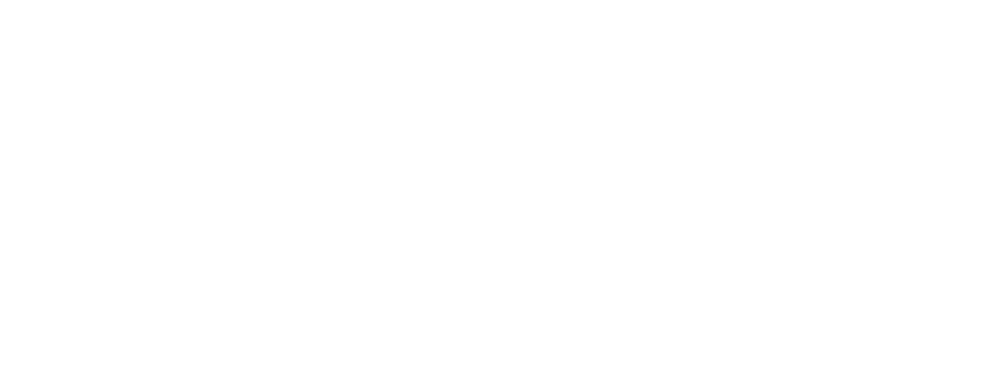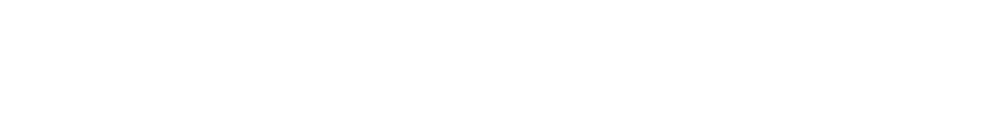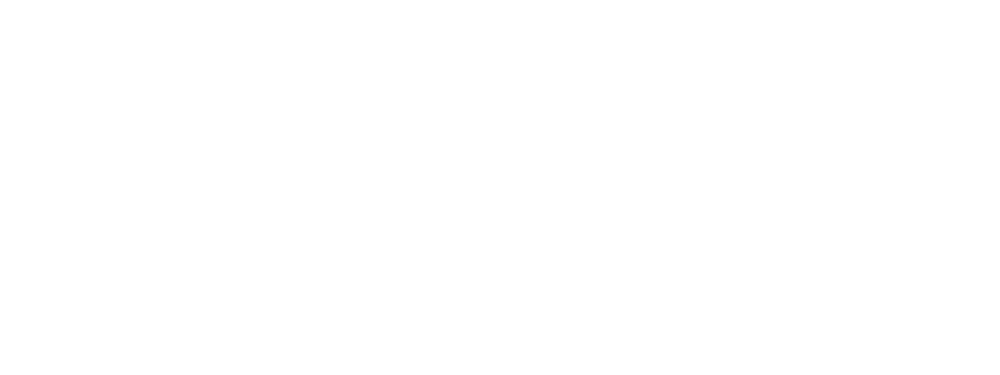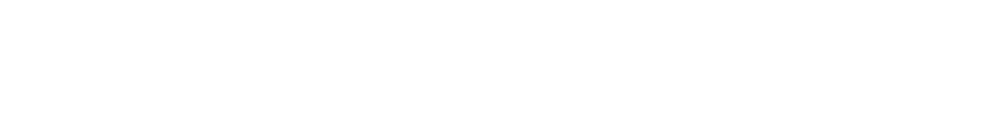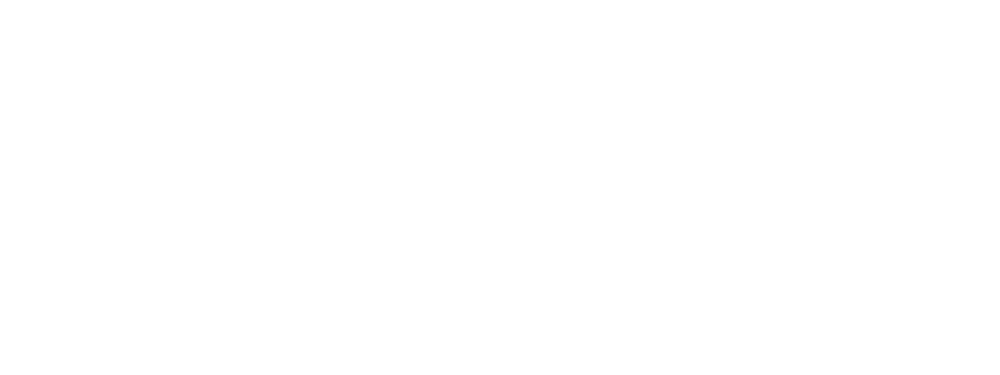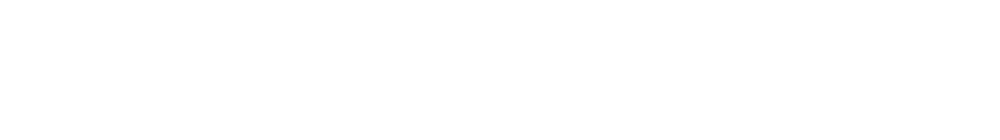霊枢勉強会報告
報告『黄帝内經靈樞』 逆順肥痩(ぎゃくじゅんひそう) 第三十八NEW
講師 :日本鍼灸研究会代表 篠原 孝市 先生日時 :令和七年(2025年) 5月11日(日) 第50回②
会場 :大阪府鍼灸師会館 3階
出席者:会場 14名
『黄帝内經靈樞』 逆順肥痩(ぎゃくじゅんひそう) 第三十八 (一部を抜粋)
○58 黄帝曰。 59 刺痩人柰何。 60 歧伯曰。 61 痩人者。 62 皮薄色少。 63 肉廉廉然。 64 薄脣輕言。 65 其血清氣滑。 66 易脱于氣。 67 易損于血。 68 刺此者。 69 淺而疾之。
58 黄帝(こうてい)曰(いわ)く、 59 痩人(そうじん)を刺すこと柰何(いか)ん、 と。 60 歧伯(きはく)曰(いわ)く、 61 痩人(そうじん)は、 62 皮(ひ)薄く色(いろ)少なく、 63 肉(にく)、 廉廉然(れんれんぜん)たり。 64 脣(くちびる)を薄くして言(げん)を輕々(かるがる)しうす。 65 其(そ)の血清(きよ)く、 氣(き)滑(なめ)らかにして、 66 氣(き)を脱(だっ)し易(やす)く、 67 血を損(そん)じ易(やす)し。 68 此(こ)れを刺す者は、 69 淺(あさ)くして之(こ)れを疾(すみ)やかにす、 と。
(解説)
*黄帝(こうてい)が歧伯(きはく)に、痩(や)せている人に針を刺すには、どのようにしたら良いのかを問うている。 歧伯(きはく)が言うには、 痩せている人というのは、皮膚が薄くて、色が浅いのだと言う。 そして肉廉廉然なのだと言う。
*63節の「肉廉廉然(にく、れんれんぜん)たり。」 とは
「廉廉然(れんれんぜん)」というのは痩せている状態を指す。 とても痩せていて、体表から骨の輪郭が見えている状態を言う。 校注を以下に記した。
*『靈樞經校釋(れいすうきょうこうしゃく)』上冊の545ページにはこのように記されている。
「“廉廉然”: 痩薄的様子。 丹波元簡: “痩臞而見骨骼。”」
*郭靄春(かくあいしゅん)氏はこのように記している。
「 肉廉廉然: 按: 《禮記・樂記》孔疏 “廉、謂廉稜。 ”廉廉然“ 是形容消痩骨立如見稜見角。 」
*廉廉然(れんれんぜん)とは、とても痩せていて、骨が体表からも見える状態のことを言う。
*64節の「脣(くちびる)を薄くして言(げん)を輕々(かるがる)しうす。」について適切な注解はない。 この文章に注を入れている注解者がいないというところに、 この部分が難解なことを示していよう。
*痩せているから、くちびるも薄くて、又ものごとを簡単に口にしてしまうということもあるかも知れない。
*「 65 其(そ)の血清(きよ)く、 氣(き)滑(なめ)らかにして、 66 氣(き)を脱(だっ)し易(やす)く、 67 血を損(そん)じ易(やす)し。 68 此(こ)れを刺す者は、 69 淺(あさ)くして之(こ)れを疾(すみ)やかにす、 と。」
*肥ってからだの中に残る場合は、その血が、にごったというふうに判断するのであろう。 氣(き)が滑(なめ)らかだと、氣がどんどんとからだの中をめぐって便(べん)や尿(にょう)として体外へ出て行くことになる。 そういうことで氣(き)を脱しやすい。 そして血(ち)を損じやすい。 そうであるから、鍼を浅く刺して、鍼を刺してから抜くまで、あるいは鍼をしてから皮膚から離すまでの時間を早くするのだと、 そういうことを言っている。
○70 黄帝曰。 71 刺常人柰何。
70 黄帝(こうてい)曰(いわ)く、 71 常人(じょうじん)を刺すこと柰何(いかん)、 と。
(解説)
*「 では、一般の人への鍼の刺し方はどのようであるか 」と、黄帝(こうてい)は歧伯(きはく)に問うている。
○72 歧伯曰。 73 視其白黑。 74 各爲調之。
72 歧伯(きはく)曰(いわ)く、 73 其(そ)の白黑(はくこく)を視て、 74 各々之(こ)れを調(ととの)えることを爲(な)す。
(解説)
*73節の「視其白黑。 【 其(そ)の白黑(はくこく)を視て、 】」について、張介賓(ちょうかいひん)という人は、このように言っている。
「視其白黑者、 白色多淸、 宜同痩人、 黑色多濁、 宜同肥人、 而調其數也。 【 其(そ)の白黑(はくこく)を視るとは、 色(いろ)白くして淸(きよ)きこと多し。 宜(よろ)しく痩人(そうじん)に同じ。 色(いろ)黑(くろ)くして濁(にご)ること多し。 宜(よろ)しく肥人(ひじん)に同じ。 而(しか)して其(そ)の數(かず)を調(ととの)うなり。】」
*おおむね、このようなことを言っていようか。
人のからだの色を視て、白い色であれば、どちらかと言えば血(ち)が澄んでいる状態で、痩人(そうじん)と同じように見るのである。 黑色(こくしょく)で多く濁っていると言う場合は、太ってる人と同じように見る。
*張介賓(ちょうかいひん)は、からだの色の白黒だけを見る場合は、そのような判断をしなさいと言っている。
○75 其端正敦厚者。 76 其氣血和調。 77 刺此者。 78 無失常數也。
75 其(そ)の端正敦厚(たんせいとんこう)なる者は、 76 其(そ)の氣穴(きけつ)和調(わちょう)す。 77 此(こ)れを刺す者は、 78 常(つね)の數(かず)を失すること無(な)かれ、 と。
(解説)
*75節の「端正敦厚(たんせいとんこう)」とは、 文字通り生活態度、からだの状態に重厚感があって、過度に食べたり、また食べなかったりすることもない状態を言う。 そういう状態であれば気血が和調(わちょう)、気血が調和するのだと言っている。
*『太素(たいそ)』という本によると「端正敦厚(たんせいとんこう)」の「敦(とん)」が「屯(とん)」になっている。
*『甲乙經(こういつきょう)』という本によると「端正敦厚(とんこう)」の「敦(とん)」が「純」の字になっている。
いずれにしても、あまりわかりやすいものでは無い。
*張介賓(ちょうかいひん)という人はこのように言う。
「 其端正敦厚者、 是即常人之度、 當調以常數。 經水篇曰、 「足陽明、刺深六分、 留十呼。 足太陽、 深五分、 留七呼。 足少陽、 深四分、 留五呼。 足太陰、 深三分、 留四呼。 足少陰、 深二分、 留三呼。 足厥陰、 深一分、 留二呼。 手之陰陽、 其受氣之道近、 其氣之來疾。 其刺深者、 皆無過二分、 其留皆無過一呼、 其少長大小肥痩、 以心撩之。」、 此即常數之謂、 而用當酌其宜也。
【 其(そ)の端正敦厚(たんせいとんこう)なるものは、 是(こ)れ即(すなわ)ち常人(じょうじん)の度(ど)、 當(まさ)に調(とと)えて、常數(じょうすう)を以(もっ)て、す。 經水(けいすい)篇に曰(い)う。 「足の陽明(ようめい)、 刺すこと深さ六分(ろくぶ)、 留めること十呼(じゅっこ)。 足の太陽、 」(**後の文は省略します。 同じ要領で読んでください。) 】
*78節の「常(つね)の數(かず)を失すること無かれ、と。」は、 それを越えるかたちで治療してはいけないと、そんなことを言っているのだ。
*『霊枢』の森を歩いてみませんか。 毎月休まず第二日曜午前10時から12時まで、大阪府鍼灸師会館3階です。 勉強会の案内につきましては本会ホームページをご確認下さい。
次回は 8月10日(日)、ふだんの『霊枢』のシリーズから外れた特別講義です。 テーマは『五藏(ごぞう)診察について』、 おもしろい、 そしてためになる。 おすすめです。
(霊枢のテキスト〈日本内経医学会 発行,明刊無名氏本〉 は現在1冊の在庫があります。1冊1,600円です。受講申し込み時、または当日、受講受付けにてお問い合わせください)
(霊枢勉強会世話人 東大阪地域 松本政己)