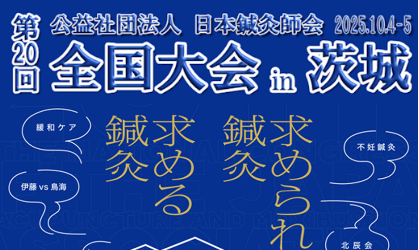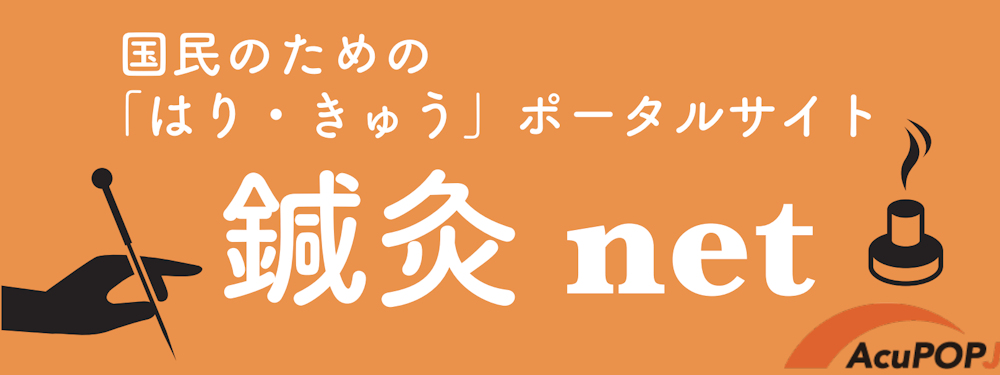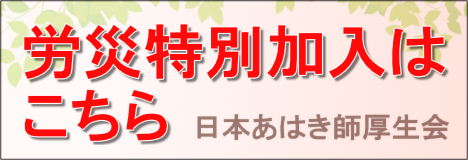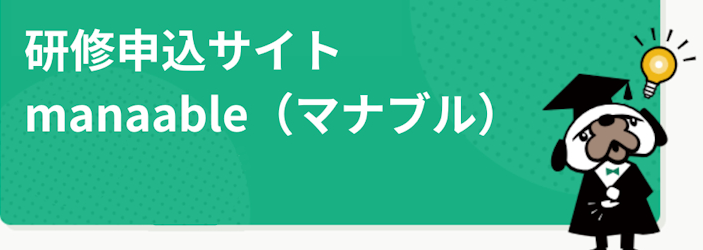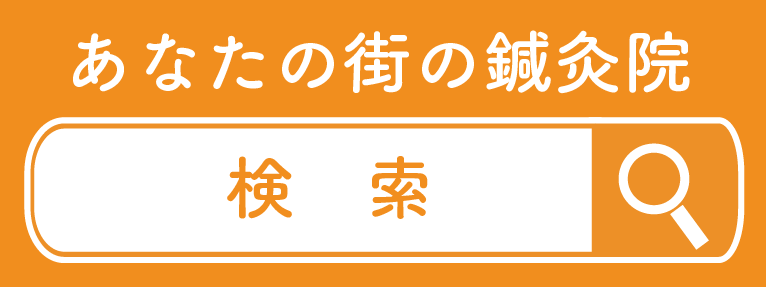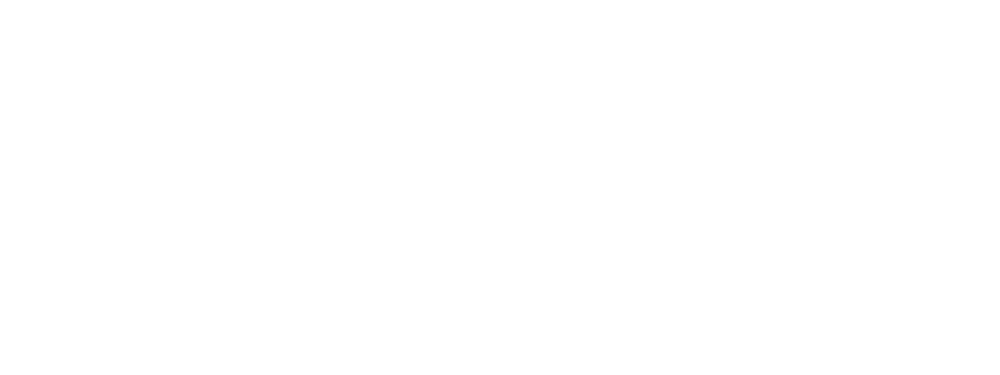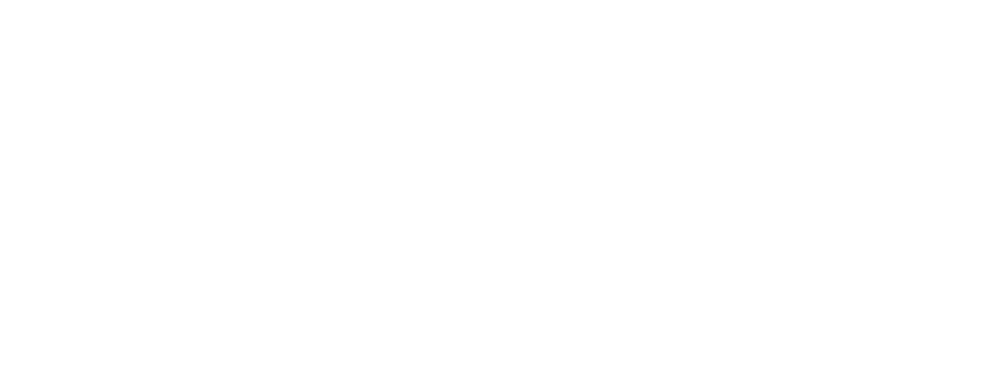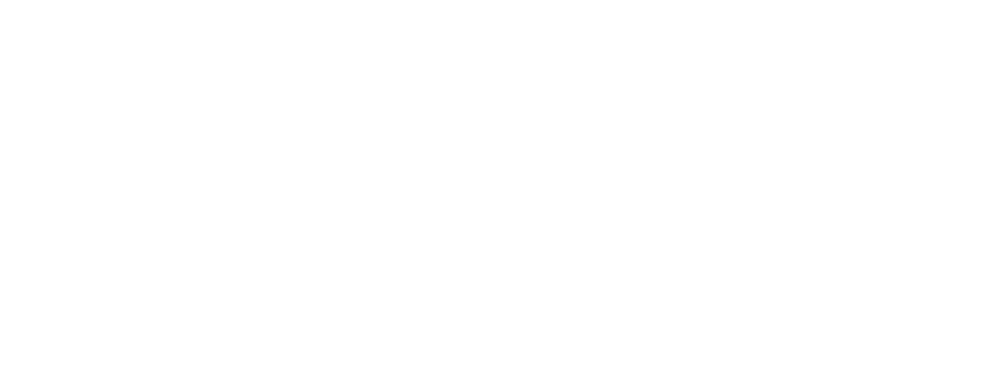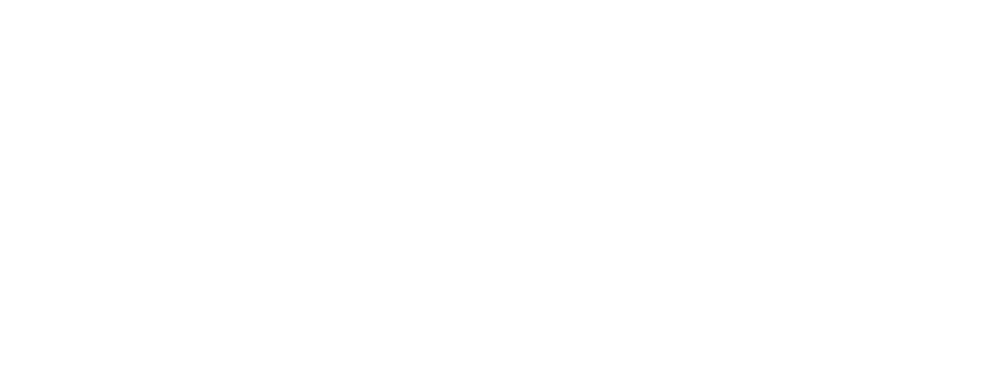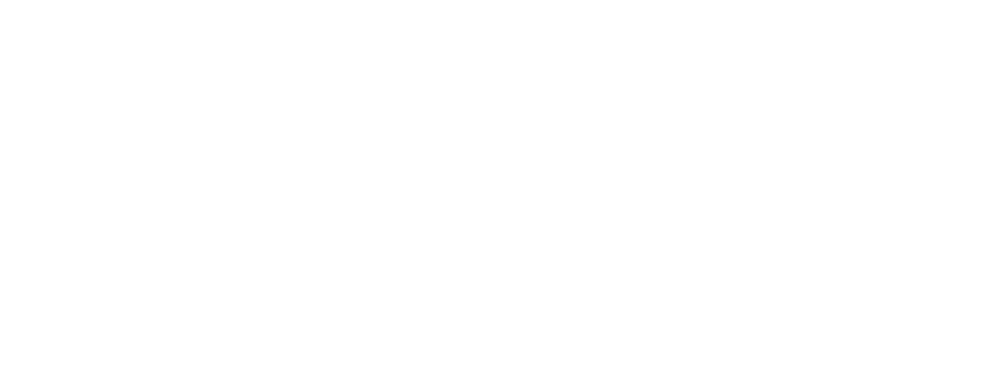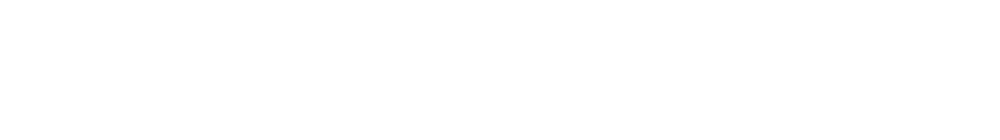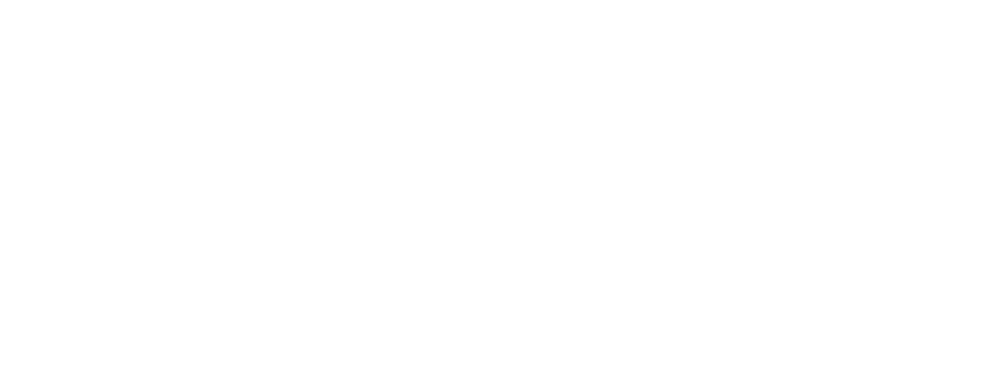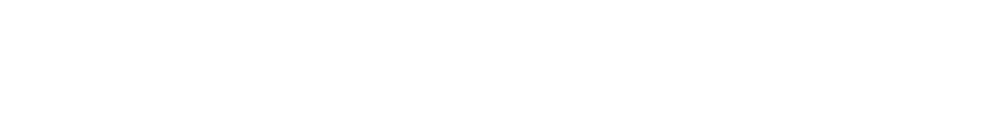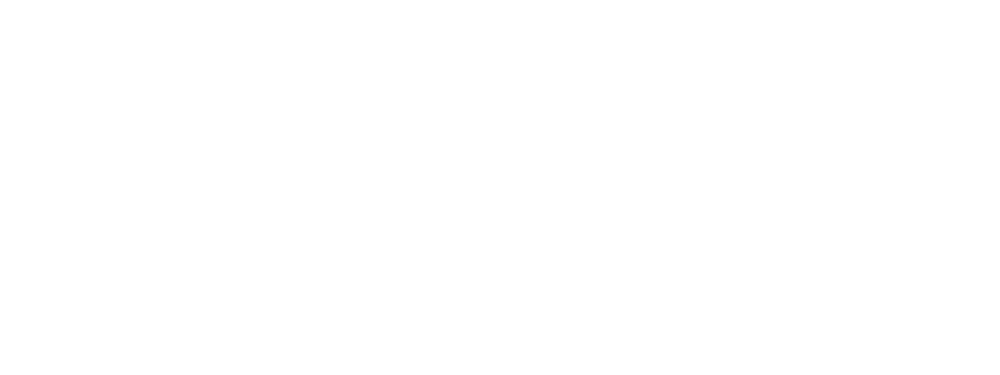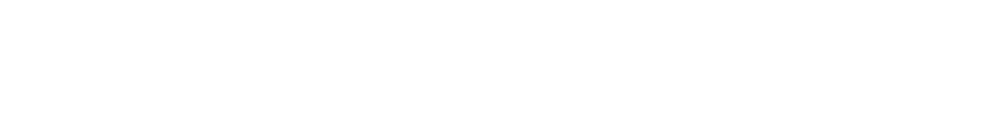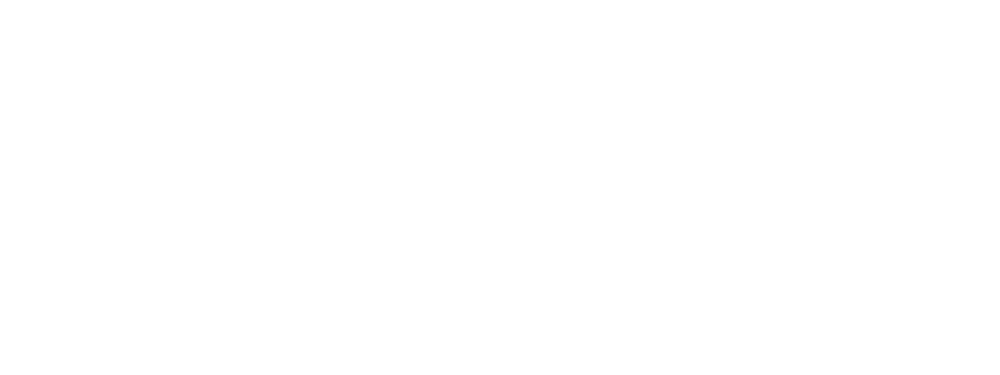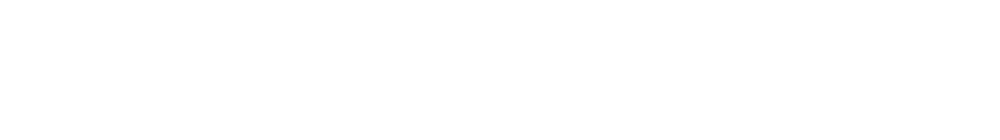霊枢勉強会報告
報告『黄帝内經靈樞』腸胃(ちょうい)第三十一
講師 :日本鍼灸研究会代表 篠原 孝市 先生日時 :令和七年(2025年) 1月 12日(日) 第46回
会場 :大阪府鍼灸師会館 3階
出席者: 会場参加者 15名 WEB参加者 24名
○『黄帝内經靈樞』 腸胃(ちょうい) 第三十一(一部を抜粋)
○24 胃。 25 紆曲屈伸之。 26 長二尺六寸。 27 大一尺五寸。 28 徑五寸。 29 大容三斗五升。 24 胃(い)は、 25 紆曲屈伸(うきょくくっしん)す。 26 長さ二尺六寸(にしゃくろくすん)、 27 大(おお)いさ、 一尺五寸(いっしゃくごすん)、 28 徑(さしわたし)五寸(ごすん)、 29 大(おお)いさ、 三斗五升(さんとごしょう)を容(い)れる。
(解説)
*25節の「紆曲屈伸(うきょくくっしん)」というのは、屈曲した状態を指す。 身をかがめた状態のことである。
*現代の医学による胃(stomach)とそれに続くものを含めて「胃(い)」と認識していたように思う。 当時は胃(stomach)と小腸(small intestine)の区別がついていたとは思えない。 この当時の「胃(い)」と称されるものには現代の医学で言う「胃(stomach)」と「小腸(small intestine)」が含まれているのではないか。
*27節の「大(おお)いさ」というのは幅のこと。
*28節の「徑(さしわたし)」というのは、ものを入れた時の直径だろう。
*24~25節の「24 胃。 25 紆曲屈伸之。」は注解書によって句読(くとう)が異なる。 25節の「之」の字が、なにしろやっかいだ。 この字が無ければ、 「 胃(い)、紆曲(うきょく)屈伸す。 」と呼んで終わりなのだが、「之」の字があることによって 「24 胃紆曲屈。 25 伸之。 【 24 胃(い)紆曲(うきょく)屈(くっ)し、 25 之(これ)を伸ばす。 】 」という句読を採用する注解書もある。
*ものを入れると三斗五升(さんとごしょう)入るという。 これは現在ではどれぐらいの容量になるかは、みなさん、換算して頂ければ良いと思う。
○30 小腸。 31 後附脊。 32 左環廻周疊積。 33 其注于廻腸者。 34 外附于臍上。 35 廻運環十六曲。 36 大二寸半。 37 徑八分分之少半。 38 長三丈三尺。
30 小腸(しょうちょう)、 31 後(しり)へ、 脊(せき)に附(つ)く。 32 左(ひだり)のほうに環(まわ)り、 疊積(じょうせき)す。 33 其(そ)の廻腸(かいちょう)に注ぐ者(もの)は、 34 外(そと)、 臍(へそ)の上に附(つ)き、 35 廻運(かいうん)し環(まわ)ること十六曲(じゅうろっきょく)、 36大(おお)いさ二寸半(にすんはん)、 37 徑(さしわたし)八分(はちぶ)分(ぶ)の少半(しょうはん)、 38 長さ三丈三尺(さんじょうさんじゃく)。
(解説)
*現代の医学において「小腸(small intestine)」は、三つに分けて「十二指腸(duodenum)、 空腸(jejunum)、回腸(ileum)となっている。 中国の古い医学で「小腸(しょうちょう)」という名前のあるものは、「胃(い)」のすぐあとに来る細い方の腸のことであろう。 腸には細いものと、太いものがあって、細い方の腸を「小腸(しょうちょう)」と名付けたのであろう。
*「小腸(しょうちょう)」というものが当時、どのように認識されていたのだろう。 背中の方にくっついているのだと考えている。
*32節の「 左のほうに環(まわ)り 」 とは、どちらから見て左側にまわるのかがわからない。 「疊積(じょうせき)」というのは、細い腸が重なっている状態を指す。
*33~35節 廻腸(かいちょう)に注ぐ部分に関しては、臍(へそ)の上に付いている。 そして16回、回っている、と言っている。
*36節の「大(おお)いさ」と37節の「徑(さしわたし)」は、全体の縦幅と縦幅である。
*37節の「徑(さしわたし)八分(はちぶ)分(ぶ)の少半(しょうはん)」の「分(ぶ)の少半(しょうはん)」というのは、一分(いちぶ)のうちの三分の一ぐらいを言う。 八分と分(ぶ)の三分の一ぐらいだと言っている。
*「38 長さ三丈三尺(さんじょうさんじゃく)」、全体の長さは三丈三尺だという。 ずいぶんと長いものである。
*張介賓(ちょうかいひん)という人は 「37 徑八分分之少半。 【徑(さしわたし)八分(はちぶ)の分(ぶ)の少半(しょうはん)】 」 について、「 八分分之少半、 言八分之外、 尚有如一分之少半也。 餘放此。 」と注解している。
*張志聰(ちょうしそう)という人はこのように言っている。
「少半者、 七分半也。 【 少半(しょうはん)は、七分半なり。 】」
*多紀元簡(たき げんかん)著 『靈樞識(れいすうし)』の注を、渋江抽斎(しぶえ ちゅうさい)は下記のように記している。
桂山先生曰、 「按 『史記』項羽紀、 「漢有天下大半」、 韋昭註云、 「凡數三分有二爲太半、 一爲少半。」。 『難經』楊註亦云、 「三分有二爲大半、 有一爲少半。」、 由此推之、 分之少半者、 三釐二毫有奇、 寸之少半者、 三分三釐三毫不盡、 寸之大半者、 六分六釐六毫不盡也、 則張註似是。 」。
上記の文を読んでみよう。
桂山(けいざん)先生が曰(い)うには、
「 按(あん)ずるに、『史記(しき)』の項羽紀(こううき)、 「 漢有天下大半。 【漢に天下大半あり。】 」 という章がある。 韋昭(いしょう)が註(ちゅう)に云(い)う。 「およそ数(かず)、三分(さんぶ)して二あるを大半(たいはん)、 三分して一あるを少半(しょうはん)と爲(な)す。 」 『難經(なんぎょう)』の楊註(ようちゅう、 【*楊玄操(ようげんそう)の註(ちゅう)であろう。】 亦(ま)た云(い)う。 「 三分(さんぶ)で二あるを大半(たいはん)という。 三分(さんぶ)で一あるを少半(しょうはん)と爲(な)す。 」 、此(こ)れに由(よ)って之(これ)を推(お)せば、 分(ぶ)の少半(しょうはん)とは、 三釐(さんりん)二毫(にごう)、奇(き)あり。 寸(すん)の少半(しょうはん)とは、 三分(さんぶ)三釐(さんりん)三毫(さんごう)に盡(つ)くさず。 寸(すん)の大半(たいはん)とは六分(ろくぶ)六釐(ろくりん)六毫(ろくごう)に盡(つ)くさず。 則(すなわ)ち張註(ちょうちゅう)、是(ぜ)に似たる。 【*張介賓(ちょうかいひん)の註(ちゅう)がいいんだと言っている。】
*ここでは、三分の二を大半(たいはん)、三分の一を少半(しょうはん)と言っている。
*『霊枢』の森を歩いてみませんか。毎月休まず第二日曜午前10時から12時まで、大阪府鍼灸師会館3階です。勉強会の案内につきましては本会ホームページをご確認下さい。
次回は 3月9日(日)、『霊枢』「脹論(ちょうろん) 第三十五」 です。 『靈樞(れいすう)』は始めからやらなきゃ、そんなことはないように思います。 どこからでも興味のある篇の受講、大歓迎です。 会場はライブ感がありますし、web受講は自宅でも出来ますので、どうぞ。
(霊枢のテキスト〈日本内経医学会 発行,明刊無名氏本〉は現在1冊の在庫があります。1冊1,600円です。受講申し込み時、または当日、受講受付けにてお問い合わせください)
(霊枢勉強会世話人 東大阪地域 松本政己)