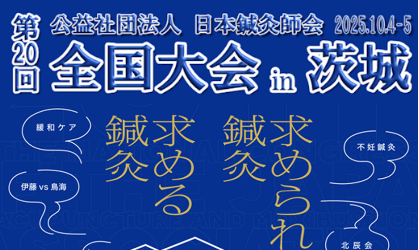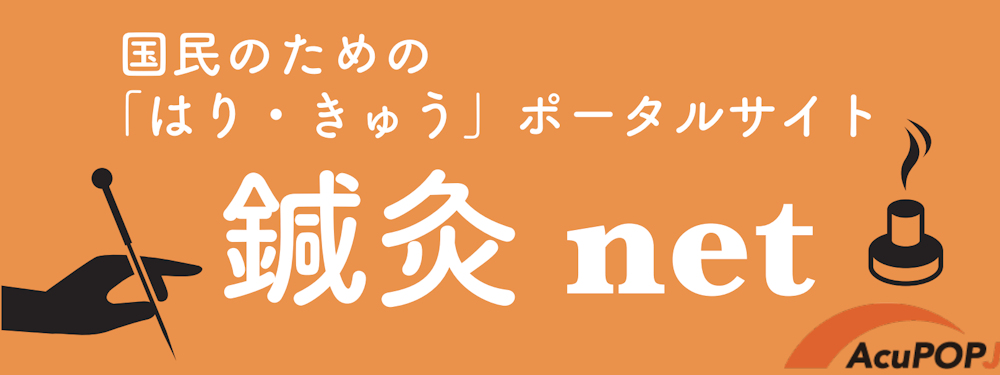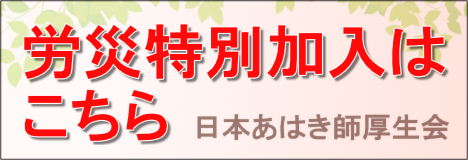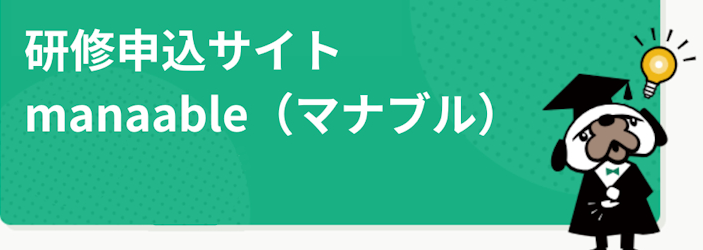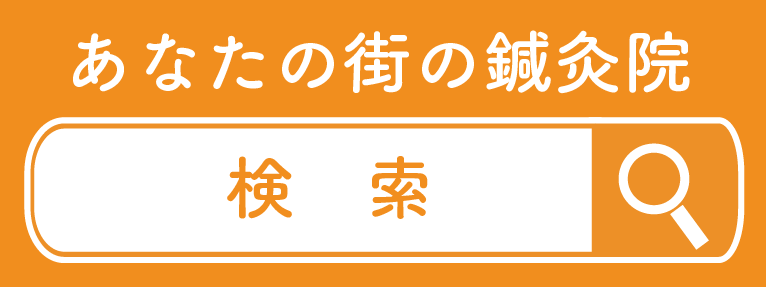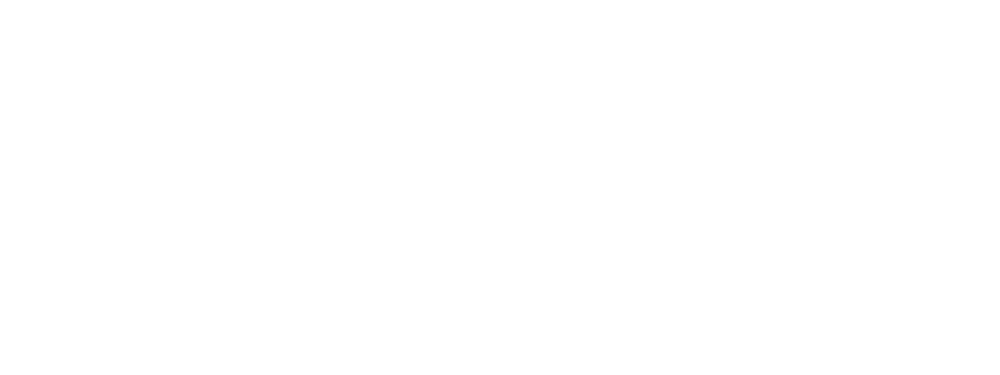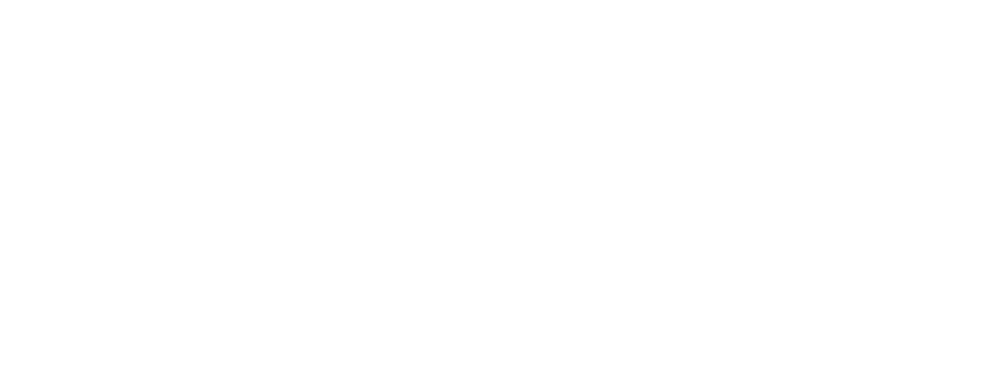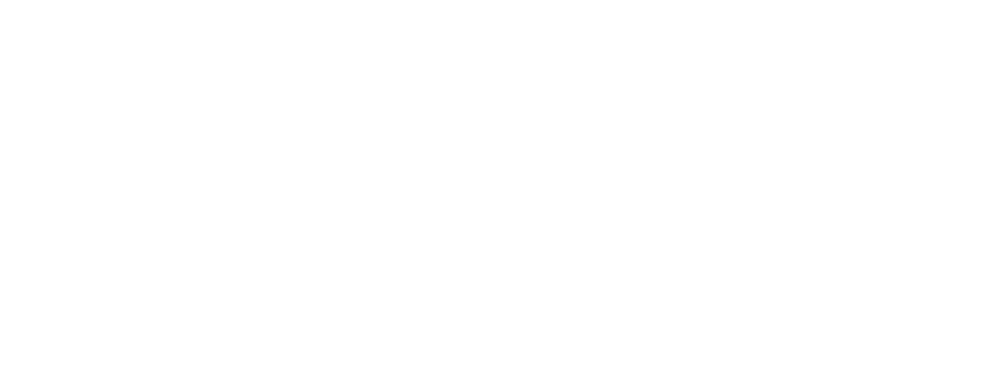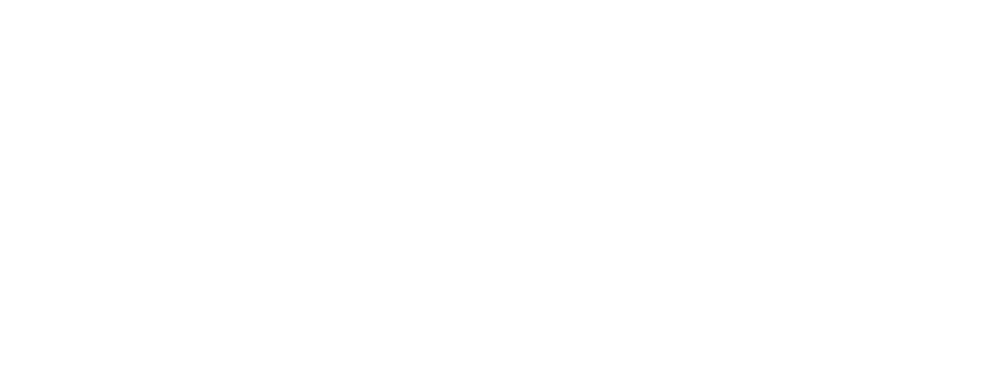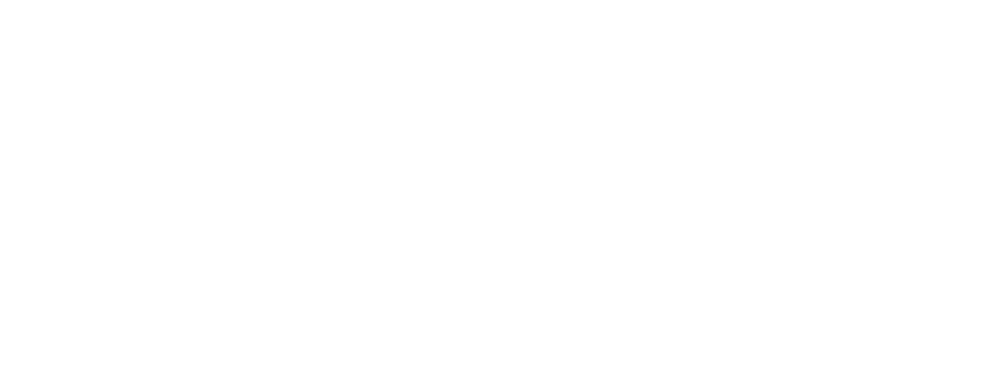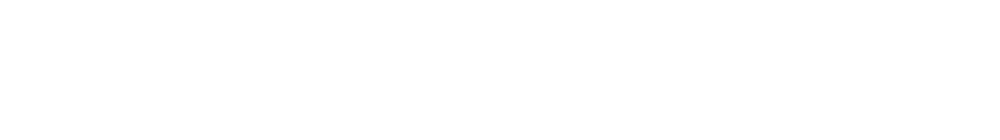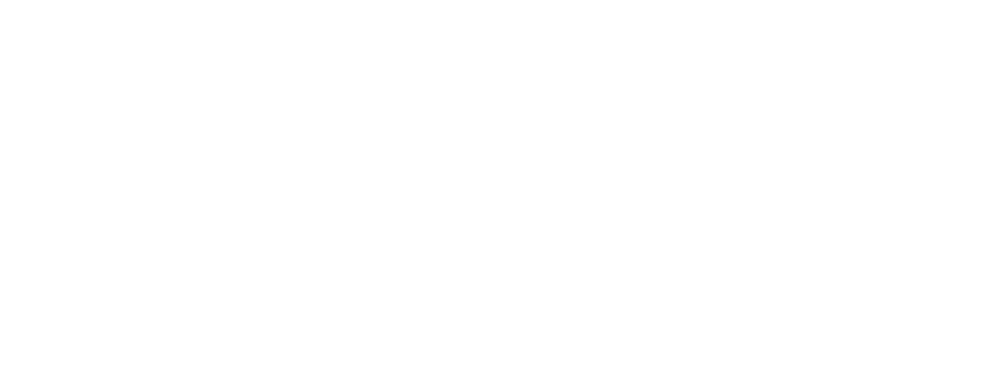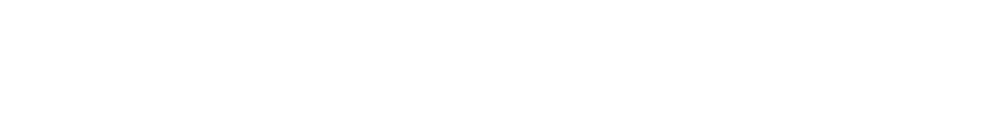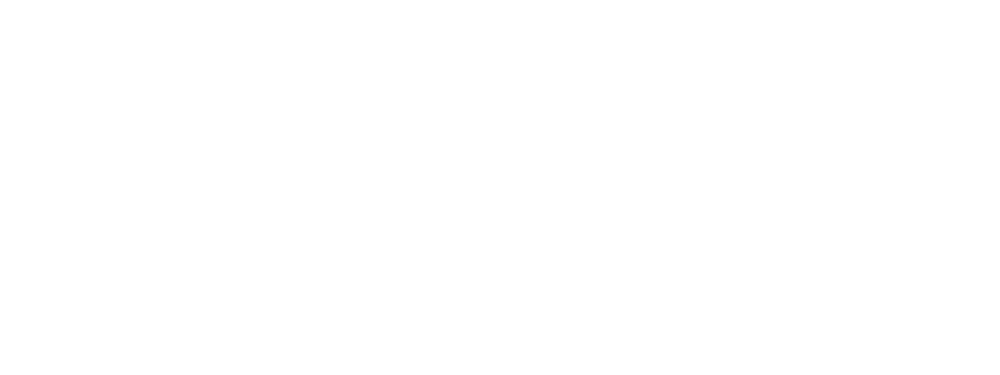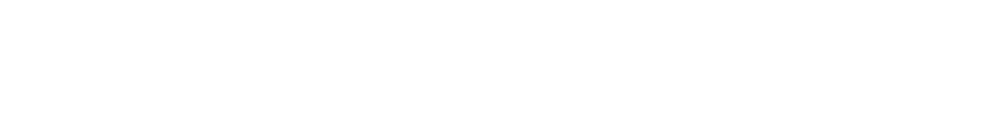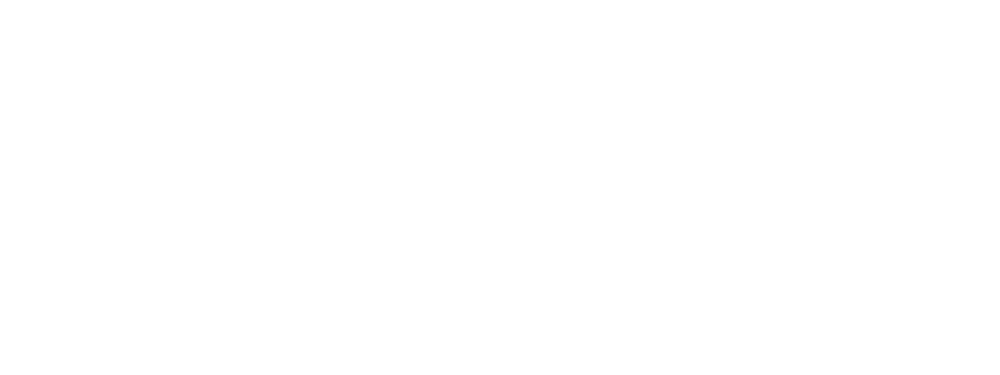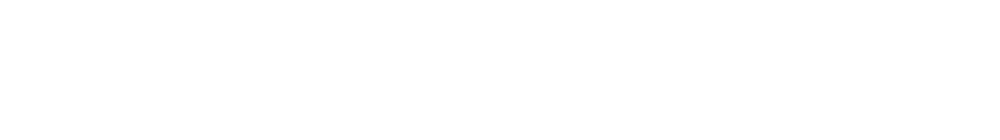報告令和6年度第5回(2月度)学術講習会
令和6年度第5回(2月度)学術講習会

【日時】令和7年2月9日(日) 13:00~16:45 学術講習会(ハイブリッド開催)
【演題】医療機関における鍼灸師の役割と将来像について
講師:小川 恵子 先生(広島大学病院 漢方診療センター 教授)
【会場】大阪府鍼灸師会館 3階 WEB
小川先生がご活躍されている広島大学病院漢方臨床センターでは、臨床だけではなく人材育成や研究にも力を入れている。広島大学病院においては漢方医学と現代医学の統合を発信しており、患者さんに健康になってもらうことが患者さんの平和へ、そして世界平和に繋がることをミッションとしている。
大学病院で鍼灸師が求められるものとは、①プロフェッショナリズム(専門性や職業倫理を重視し、社会や人間に貢献していくこと)②コミュニケーション能力と共感(鍼灸師はチーム医療の一員であり、カンファレンスで治療方針を決めていく。電子カルテを利用)③現代医学や湯液の知識(湯液と鍼灸は車の両輪)である。
鍼灸師は湯液の勉強もしており、鍼灸治療との相乗効果についても研究している。日本の漢方治療の特徴とは、医療用漢方製剤(エキス剤)148方剤、調剤用生薬約200種類あり、医師の診察により健康保険で薬剤投与を受けられ、また品質・安全性が管理されているということ。
そもそも漢方の定義とは、湯液と鍼灸と推拿である。しかし日本では多くの場合、医師が漢方薬を出しており、鍼灸師は漢方薬の知識が乏しい傾向にあるため、漢方医学全体の知識が足りないと問題提起されている。
漢方処方が有効だった例として、①小児(1歳)の人工肛門造設し閉鎖した後の下痢・便秘・不機嫌・夜泣きに対して小建中湯・抑肝散が著効。②先天性のリンパ管奇形(難病)の疼痛・腫脹に対して越婢加朮湯・黄耆建中湯で著効。③9歳女児の急性骨髄性白血病(骨髄移植後)において、免疫抑制剤投与中で下痢と食欲不振があり、薬剤投与は困難のところ、小児鍼治療(大腸膀胱経と腹部、全身の擦過)により著効。など、その他難病にも多くの効果がみられ、鍼灸治療の良さは主訴だけでなく全体が良くなるというのが強みである。また湯液は薬に比べるとコストの大幅な削減にも注目されている為、研究が進むと世界中の困っている患者さんにも広く提供できる可能性がある。
ただ現状における医療連携の問題点として、医療の選択肢として鍼灸がまだまだ無い為、大学病院では人材育成に力をいれ、10年前より卒後教育制度を確立している。モデルケースを作り、持続可能な病院鍼灸を可能にするのが目標。
例えば顔面神経麻痺の症例では鍼灸が主役になるように、漢方統合医療は、非常に患者さんに有益である。
また、コロナウイルス罹患後の後遺症によくみられる食欲不振や倦怠感の症状に対して、西洋医学的視点(脳の炎症の慢性化に対する薬剤)と東洋医学的視点(気鬱・気虚に対する漢方)から全体的な不調を総合的に認識する治療を行っている。
今後医療は診断サポートシステムの開発により、誰でもできることはAIに代わられる可能性があるが、五感に基づく診断や手技的なことは鍼灸師しかできないため、多くの鍼灸師が是非病院と連携を取って、また自信を持って今後も取り組んでほしいとエールをいただきました。

【実技】経方医学に基づく診察法と鍼灸法 廣瀬桂子先生
診察法では主に脈診、腹診、皮膚の状態や四肢のむくみ、骨格のバランス、筋肉の凝り、寒熱などをみる。
[脈診]
右手で肺・脾・腎、左手で心・肝・腎をみる。また寸口は上焦、関上は中焦、尺中は下焦をみる。さらに浮沈(深さ)、大小(幅)、滑渋、数遅、弦、有力無力なども確認し、証をたてる。
[腹診]
心下は剣状突起の下から肋骨の方へ圧迫し、呼気で痛み→宣発機能失調、吸気で痛み→腎の粛降機能失調。胸脇苦満で真ん中が痛い場合は胸を反映し、端が痛い場合は隔を反映している。
腹直筋緊張については、上部と下部どちらがきついのか確認。腹部動悸については水飲、気逆のサインを示しており、3パターンあり(心下悸、臍上悸、臍下悸)。
小腹に関しては下腹部圧痛(瘀血)、小腹不仁(腎虚、小腹が軟弱)をみる。
[本治法]
経気鍼…経絡の気の調和を目的とし、鍼尖を経絡の走行に沿わせ、表皮に30~40°の角度で接触する。経穴から鍼の振動を伝え経絡の気を流す。気が至ったと感じたら抜鍼する。
臓腑鍼…臓腑の気の調和を目的とし、鍼尖を臓腑に向け、表皮に垂直に接触させ3~5呼吸ほど押し手を沈めていく。体表近く(陽)と臓腑(陰)の気を往来させ陰陽を調和させる。少し深い所をイメージする。

[各証で使う経穴について]
経気鍼については肝虚(曲泉)、脾虚(太白)、腎虚(復溜)、肺虚(太淵)、心虚(神門)、その他臓腑鍼については墓穴と兪穴。また実際に使われる経穴によってはWHOの国際基準の場所と少し異なるということで、具体的に曲泉、太白、期門について解説していただいた。
[標治法]
肌鍼…最初に行う。腹部4点と肌(真皮・脂肪)の虚に施行。真皮・脂肪部の陥凹や無力な部位に対して行う。
推動鍼(肌肉の気を調整)…肌絡・邪実・肉絡の滞りに対して施行。皮下脂肪-筋膜筋肉部の硬結や水滞・気滞・瘀血に使用する。邪実の側面を狙って斜め45度位で当て補気をし、自ら動いてもらう目的で行う。
散邪鍼(経絡と肌肉の気を調整)…推動鍼で動かない肌絡-肉絡の滞りに対して施行。皮下脂肪-筋膜筋肉部の硬結や水滞・気滞・瘀血に使用する。経絡の滞りに対しても施行。邪実の側面を狙って斜め45度位で当て押し手を使って少し雀琢を加える。経絡に熱や実邪がある場合(主に脈で判断)、その経の絡穴や郄穴を瀉する。
皮気鍼(皮気の調整・補法)…鍼尖を皮膚に接触させ、直角に立て左右にねじる。痺れや腠理の疎がある場合に使用する。むくみにも効果あり。
散鍼(皮気の調整・瀉法)…皮気の鬱滞を軽く流す。連続的に鍼尖が皮膚に触れたと同時に鍼を引く。腰背部に多い、黒ずみやザラザラするような皮気の鬱滞部に施術。
調整鍼(皮気の調整、仕上げ)…散鍼とセットで使い、皮気を滑らかにする。連続的に鍼尖で皮膚に触れ、皮気を調整する。皮膚が滑らかに潤いを持ったらその箇所の施鍼は終了する。
引き鍼(気を引き遠隔の邪を散らす)…問題がある場所の疎通を目的とし、斜め45度に鍼を当て患部から気を引き邪気を散らす。病症に従って特効穴を取穴。(例:腰痛の治療の場合、最後にもう少し効果を出したい時に、膀胱経の崑崙や委中から引いてくるイメージ。経絡を疎通させる)

[実技(本治法)]
まず腹診で圧痛と緊張の部位を把握。関元・中脘・天枢に接触鍼(銀鍼)をすると脈が分かりやすくなる。右の尺中が沈細渋で腎虚と診断し、復溜に経気鍼(男性は左→右側の順)。左右腎兪(兪穴)に臓腑鍼。呼吸に合わせて気を交流させる。続いて左右京門(募穴)。臓腑鍼をすると患者さんの呼吸が深くなることもある。接触鍼が効いているがどうかは最終的に脈診で判断する。(この時は沈→浮へ変化し、弦も一部とれてきた)これらの本治法は全体のバランスをとる治療で、癌に伴う倦怠感など、本治法だけでも楽になる場合もあり、気が足りなくてあまり刺激ができない患者に最適。
治療は全て接触鍼で行われ、丁寧にツボの反応をみながら細かい手技を駆使して調整されていました。実際の臨床では、さらに症状に応じて標治法も加えて脈を整えていくとのことで、このような治療には指先や気の感覚を鍛えていく修練が非常に必要だと感じました。病院で東洋医学的な伝統的な治療が行われ、研修制度が確立していることに驚きました。今後も、困っている多くの患者さんに、各地域でも鍼灸師が高いレベルの治療を提供できるように、また受け入れ可能な場合は発信していけるように、鍼灸師間の連携は勿論、医療従事者の一人として協力していく重要性を強く意識させていただいた機会となりました。
(研修委員 上田里実)
【日時】令和7年2月9日(日) 13:00~16:45 学術講習会(ハイブリッド開催)
【演題】鍼灸師の未来像となり得る電子カルテの活用方法
講師:伊藤和憲先生(明治国際医療大学 鍼灸学部 学部長)
【会場】大阪府鍼灸師会館 3階 WEB
鍼灸師に電子カルテはいらないのか。近時では保険証のオンライン資格確認が開始され、医療の電子化がすぐ身近なところまで来ていると感じます。電子カルテの導入についても、メリット・デミリット以前にその迫られている必要性を、さらに、これからの鍼灸師や地域医療のあり方に深く関わっていくものだと今回の講義を通じて知ることができました。
①電子カルテが必要とされる背景
・国はビッグデータ化をすすめている。今後、医療を含む社会保障費においてもビッグデータを元に適正化されていく。ビッグデータを構築していくためには電子カルテが必要。
・電子カルテの使用とマイナンバーカードの保険証利用により、その医療機関の中だけでなく全国どこからでもより精度の高い情報の共有が可能になる。
・医療ではオンライン化は着実に始まっており、医療保険のレセプト請求は100%のオンライン化を目指している。
・レセプト請求のオンライン化では、作業の無駄や間違いを防げる事に加えて、AIを活用した不正請求の監視が可能になる。
・電子化は、様々な医療関係データをまとめて最適な医療を受けられるようにビジネスや社会、生活の形・スタイルを変えていく試みである「医療DX(デジタルトランスフォーメーション)」のためにもすすめられている。
・さらに、医療DXはヘルスケア分野の中の1つに過ぎず、最終目標は様々な生活データを集めて統合し、快適な社会の実現をめざす「デジタル田園都市構想」にある。
つまり、国がこれから目指している社会は医療においても生活においてもデジタルで統合された社会であり、電子化の中に入らなければ鍼灸師は医療からも社会からも取り残されてしまうことになります。現在、鍼灸はビッグデータ上にも医療DXのシステムにも含まれておらず、このままでは医療から省かれる事にもなりかねず、今後、電子カルテの導入をはじめとした電子化の流れに乗らなければ鍼灸師の立場は更に悪くなってしまう事が考えられます。
ここで注意しないといけないのが、これらの電子化に対応するためには、クラウド型の電子カルテで、さらに構造化したデータ(Excel解析できるもの)として記録できる電子カルテを使用しなくては意味がないという事です。このような電子カルテを「標準型電子カルテ」と呼びます。現在、国はビッグデータ化のためにもこれらの標準型電子カルテの普及を急速に進めています。
また、電子化にはAIやクラウドを活用したメリットが多く存在する事も確かで、電子カルテにも記録のためだけでなく、鍼灸師の業務や臨床を助けるメリットがあります。今後、大阪府鍼灸師会の会員に提供予定の伊藤先生が開発された電子カルテ「COMO」も、鍼灸師が抱える問題をサポートして、治療者のアピールもできる電子カルテになっています。
②COMO 正式名称:コミュニケーション・メモ
電子カルテの標準型機能に加えて、予約管理、予診票の使用も可能。また、従来の電子カルテと違う4つの点として、
1. 個人アカウントを治療院アカウントでまとめる・・・SNSのように個人単位でアカウントを作り、それをグループアカウントで束ねる事により、従来のように治療院でのカルテとしてだけでなく個人の臨床履歴としても電子カルテの記録が残せる。
2. 患者情報を地域で共有・・・医療だけでなく患者さんの地域の情報も共有できる。
3. 治療者の自己肯定感が高まる・・・自身の臨床履歴が残る事で得意分野、苦手分野などが見える化できるようになる。宣伝や得意分野の根拠にもできる。
4. 基本部分は無料・・・カルテの基本機能は無料なのでAIの使用等をやめてもカルテの記録はそのまま残せる。
このように、カルテとしてのデータの記録にとどまらず、個人の臨床履歴としても残すことができ、そのデータを様々な場面において使用できる仕組みになっています。その他、
・予測診断とレッドフラッグ
・治療目的に応じた標準治療を教えてくれる
・東洋医学的診察もサポート
・医師への紹介状の作成も可能
等の機能も備わっており、AIの力を駆使して鍼灸師の業務のみならず、臨床や経営もサポートできる仕様になっており、様々な面で鍼灸師の味方になりうるカルテだといえます。
③電子カルテを活用した未来像
伊藤先生は、さらに電子カルテやAIを用いた先に、社会と繋がる未来像を考えておられます。
これからは、健康寿命に加えてどれだけ幸せでいられるかのwell-beingの概念が重要であり、そのためには医療だけでなく地域とのつながりを重視した「社会的処方」が必要だと仰っています。体調管理アプリ「YOMOGI+」では健康を東洋医学的な視点で点数化できるだけでなく、適した生活習慣や地域活動の紹介もできるようになっていく予定です。YOMOGI+とCOMOとの連携で患者さんに係る医療から地域の情報に至るまでも共有できるようになり、これらの仕組みを使って鍼灸師が医療連携と地域連携の架け橋となるような社会を目指されています。
今回の講義は急遽アーカイブでの開催となりましたが、伊藤先生の電子カルテや鍼灸師、地域医療の未来に対する熱意が大変伝わってくる講義でした。
昨今では日常生活でもIT用語を聞く機会はかなり増えましたが、講義を通じてIT用語がとても多いのが印象的でした。それも医療や社会が向かう方向性を知ると確かに納得。鍼灸師の今後を考えると電子化は避けては通れないと感じたと同時に、電子化を利用した今後の鍼灸や地域医療での養生の可能性に大いに希望が膨らみました。
(大阪府鍼灸師会研修委員 片岡昌彦)